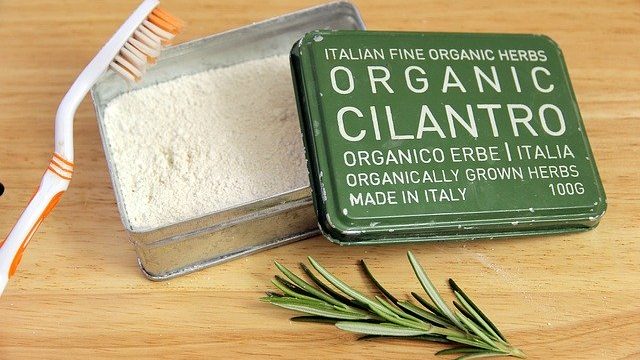こんにちは、宮比ひとしです。
この記事では、オリジナル小説である『おかえんなさい、ラブマネさん』その10を紹介します。
おかえんなさい、ラブマネさん その10

恋愛保険の相談窓口となる恋愛支援専門員(ラブマネージャー)の青年が、個性豊かな利用者の恋愛支援に奮闘するラブコメ小説となっています。
登場人物の紹介
影沼洋一・・・美鷹恋愛支援センターに勤務する新人ラブマネージャーであり、本作の主人公。
野山愛子・・・影沼洋一と同棲中の交際相手。
花岡百永美・・・影沼洋一が担当する女子大生の利用者。
富樫烈久・・・花岡百永美の交際相手。
大空夏樹・・・影沼洋一が担当する金髪ギャルの利用者。
坂本浩介・・・大空夏樹の交際相手。
濱崎極・・・影沼洋一が担当する定年退職した男性利用者。
濱崎弘子・・・濱崎極の妻。
山田直也・・・影沼洋一が担当するオタク青年の利用者。
中谷舞・・・靴屋『エムメス』の女性店長。
四谷高夫・・・美鷹恋愛支援センターの所長。
一ノ瀬友子・・・影沼洋一の世話を焼く中年上司。
六本木美加・・・影沼洋一の先輩ラブマネージャー。
新田貴彦・・・元諏実高校野球部の男性。
新田伸枝・・・新田貴彦の妻。
前回までのあらすじ
濱崎極との離婚を決意した弘子。
影沼洋一は、両親が小さな行き違いから離婚したため、必死に説得する。
濱崎極と弘子は二人でもう一度話し合うこととなったものの、洋一自身は両親の離婚後一人で過ごした少年時代と、愛子が出て行った今の状況を重ね合わせ・・・









十一月二十八日 月曜日
ベッドランプの薄明かりの中、阿修羅が憤然と睨みつけてくる。百永美は烈久の背中に彫られた阿修羅から目を逸らし、口元まで毛布を捲し上げた。彼は煙草を燻らせつつ、携帯電話をいじっている。
いつものこと。いいえ、少なくとも以前は事が終えるまでは百永美を見つめ、話をしてくれた。武骨な手を重ね、強く愛撫してくれた。しかし顔に痣ができてからというもの、一度も抱こうとしなかった。彼にとって自分の存在意義は何なのか。会話もふれ合うこともなく、ただ彼は寝床を求めて戻ってくるだけだ。百永美は唇を咬んだ。
突然、烈久がチッと舌を鳴らしたので、反射的に身が強張った。嫌なメールでも送られてきたのか。彼は携帯電話を通して不機嫌になることが度々あり、そんな時は決まって八つ当たりする。
むくりと半身を起こすと、彼は煙草の箱をくしゃくしゃに丸め、素肌のままジャージに腕を通した。「煙草買ってくる」
「あ、うん」
よかった。どうやら煙草が切れただけのようだ。
「財布借りるぞ」
瞬時に心臓が萎縮した。そして墓場に流れる夏の夜風のような冷ややかで霊的な空気を背筋に感じた。私が買ってくる、そう言おうとするも、すでに彼は百永美のバッグから発見したそれに目を奪われていた。
彼が手にしているのは、洋一がポストに入れた虐待防止のパンフレットだった。
「違うの。それはラブマネが……」
弁明する間もなく彼の掌が視界を遮る。床に引き倒され、百永美は悲鳴を上げた。アイロンでも押しつけられたかのように頭皮が焼ける。烈久の指先には息絶えたハリガネムシみたいに毛髪が巻きついていた。さらに無表情のまま下腹を蹴りつけてくる。
口から嗚咽が洩れた。女とは思えない、いや、人ではない。それは牛のように野太い嗚咽だった。
彼は百永美に跨り、何度も何度も殴りつけた。痛みが痛みを重ね、徐々に感覚が鈍麻していく。他人事みたいに。高校の社会科で流されていたつまらない映画を観ている気分。早く終わんないかな。早く意識を失わないかな。いつものように。
水中でゴーグルをかけているように、ぼやけてきた。瞼が腫れ塞がっているせい? 違う違う。これは意識が遠のいていく瞬間。もう少しもう少し。もう少しの我慢。ねえ、もう少しって、いつまでなの。いつまで続くの?
ゴーグルを剥ぎとられ水の底へと沈みゆくように視界が滲む。涙が溢れ出ていた。
――暴力をふるうことが愛情表現なんて間違っています。
他人のあなたに何がわかるの?
――わかりませんよ。わかりっこない。わかりたくないです。
私だってわからないよ。なんでこんな目に合わなきゃいけないの。どうして私なの? でも烈久には逆らえない。怖いの。だからお願い、そっとしておいて。
――そんなこと僕にはできません。
目を開くと、そこに烈久の姿はなかった。全身にイバラが巻きつき、皮膚へ食い込むかのような激痛が襲う。百永美は悶えながらもバッグまで這いずった。御守を握りしめ、仰天した。金色のはずの御守が真っ赤になっている。それは断ち切ることのできない不吉な運命を暗示させた。眩暈がする。逃れることができない運命に身を委ねるようにうなだれた。
――あなたは傷ついている。
うん、そうみたい。
――心に深い傷を負っている。
ねえ、私どうしたらいいの?
――僕があなたの恋愛支援専門員です。
烈久によって打ち砕かれていた勇気の欠片が煌めいた。ラブマネージャーの言葉が頭でリフレインする中、その欠片を掻き集め、瞼をこじ開ける。真っ赤なのは御守だけでなく、手も上着も染まっていた。血だ。まがまがしい赤い糸を引きちぎり、よろめきつつキッチン台の蛇口を捻る。御守を水で洗い流しながら百永美は決心した。
玄関扉の開く音がした。烈久が戻って来たのだ。
百永美は急いで携帯電話を操作し、叫んだ。
「助けて!」
まるで鈍器で後頭部を殴りつけられるかのような衝撃が走った。携帯電話がジリジリと鳴り響いている。枕元の眼鏡を嵌めた。夜光に照らされたボジラの目覚し時計の短針は二を差していた。深夜の二時だ。誰だ、こんな時間に不謹慎な。まさか愛子? 慌てて鳴り続ける携帯電話の通話ボタンを押した。
「もしもし、影沼くん?」
男の声だった。聞き慣れた声であるが寝ぼけているせいで、はっきりと顔が浮かんでこない。
「四谷だ。花岡百永美さんは影沼くんの担当だったね?」
眠たそうな四谷所長の表情がまず思い浮かんだ。が、いつもの彼とは似つかわしくない緊迫した声質だった。湖に張った氷上を歩くように慎重さと危険をはらんでいた。
「はい、そうですが。こんな時間に一体……」
「センターから転送で電話があった。女性が助けて、そう一言残して切れてしまったんだ。履歴を調べると花岡さんの携帯電話からだったよ。影沼くん、なにか心あたりはないか」
洋一は息をのんだ。
「影沼くん? 聞こえているか」
「彼女のところへ向かいます」
電話を切ると、夜のとばりを裂く勢いで自転車のペダルをこぐ。彼女のアパートに着くと玄関扉を殴りつけ百永美の名を叫ぶ。ノブに手をやると鍵は掛かっていなかった。無我夢中で部屋に飛び込んだ。
ベッドの手前で百永美が横たわっていた。神様にでも懺悔しているような姿勢でぴくりとも動かない。うっすらとしたベッドランプの灯りが床に飛び散ったどす黒い沁みを照らしている。血痕だった。
「大丈夫ですか!」
洋一が抱き起こすと、彼女は別人のように顔中が腫れ、鼻はあらぬ方向に捻じれ、いたるところ鮮血にまみれている。状況を把握するには充分だった。男に殴られたのだ、それも執拗に。雷鳴を轟かせ、うねる黒い荒波にのまれるのを洋一は感じた。未然に防ぐことができなかった後悔が襲う。肩を抱く手に力がこもるのを抑えられなかった。
百永美の睫毛がぴくりと跳ねた。かすかに瞬きをし、塞がりかけた瞼から黒々とした瞳でたしかに洋一を捉えた。そっと袖をつかみ、微笑む。そして母におでこを撫でられながら寝床に就く幼子みたいに穏やかに沈んでいった。
舌打ちが鳴る。
ベッドの上で胡坐をかき、煙草をふかす男がいた。露わになった上半身はまるで豹のようにしなやかで引きしまった体躯だった。
「なに勝手に入ってきてんだよ」男はぽつりと言った。
そこに怒りは感じられなかった。紛れ込んできた虫に対してでも呟くような心ない響きだ。男は罪悪感なく殺虫スプレーを噴射するみたいに無感情な眼つきを向けていた。その途端、ちっぽけな存在である虫がどうあがいても太刀打ちできない強大な敵と遭遇したかの恐怖の念に駆られた。洋一の足が竦む。
「誰? あんた」男は灰皿で煙草を揉み消し、立ち上がった。
「花岡さんの恋愛支援専門員の影沼と申します」洋一は深々とお辞儀をした。
「こいつのラブマネージャーがなんの用? こんな夜中に。何時かわかってるのか」
腕時計を覗き込んで言った。「午前二時三十四分五十秒ですね。仰る通り非常識な時間であること、心からお詫びします」
ジャージズボンから出したジッポーライターをカチリと鳴らし、男は煙草に火を燈した。男の顔が橙色に燃える。きめ細やかで端整な容姿だが感情が欠落したように感じるのは変わらなかった。氷のマスクみたいに異様だった。
「で、一体なんの用なわけ」
冷気を纏うかのように男は口から煙を吐き出した。
「花岡さんから救済の要望がありました。それにこの怪我……なにがあったのでしょうか。経緯を説明願います」
男は何も答えない。煙の行方でも追うように天井を見上げていた。
「とにかく救急車を呼びます。話はその後にしましょう」
携帯電話を取り出すと、男の脚が鞭のように洋一の腕を打ちつけた。
「余計なことするんじゃねえよ」
床に落ちた携帯電話を男が蹴り、部屋の隅へと弾け飛ぶ。
「少し怪我したくらいで大袈裟なんだよ。後で手当てしておくから、もう帰ってくんない」
「少し……この流血が少し、でしょうか」
「そんなことはどうでもいいんだよ。早く俺の家から出てけよ」
「どうでもよくはありません。それにここは花岡さんが賃貸契約しているアパートです」
「あんたもわかんない奴だな。俺はこいつと付き合ってんの。同棲してんだよ」男は親指でこめかみをこつこつやる。「頭悪いんじゃないか」
「お答えいただきたい。この怪我あなたがやったんですね?」
準備運動でもするように男は肩を竦め、首をぐるりとまわした。「だからこんな七面倒なこと嫌だったんだよ」不意に男の視線は百永美へと向けられた。ゴミ箱に棄てようにもふれるのも躊躇う、ぼろぼろに使い古された雑巾でも見るような冷たい視線だった。
嫌な予感がした。
「お前が余計なことするからだよ、なあ聞いてんのか」男は舌打ちをして、彼女の腹を蹴り上げる。吊られたサンドバッグが落ちるような重々しく乾いた音がした。
「おやめなさい」洋一は二人の間に割って入る。
すると喉元を突かれるように襟をつかみ上げられた。身長はほとんど変わらないはずなのに男の頭頂部が見える。呼吸ができないまま壁へと押しやられる。宙に浮く脚をばたつかせるが、チェーンの外れた自転車ペダルをこぐように虚しく空まわりするだけだ。男の腕を引き離そうにも樫の木の如く硬く強靭でほどくことができない。しだいに意識が薄れ、口からよだれが溢れ出てきた。
もうダメだと思った時、腕から解放され洋一は尻餅をついた。男は顰め面で手をぬぐっている。どうやら蟹の泡吹きさながらのよだれに救われたようだ。
男は洋一を睨みつけた。「さっさと出てけよ。これは俺たち二人のことだ。あんたに関係ねえだろ」
洋一は胸を張って手を広げる。大きく息を吸い込み、ゆっくりと吐いた。繰り返し三回深呼吸。そして男を睨み返した。「そういうわけにはいきません。僕は彼女の恋愛支援専門員です」
窓が開け放たれたように空気が流れた。窓は開いていないし、カーテンも動いていない。ただ伏せている百永美の髪が揺らいで見えた。見間違えかと思ったが男も彼女を凝視していた。彼女の位置だけ地震でも起きているみたいに小刻みに揺れている。
「お願い、出て行って」彼女は声を震わせた。
男は鼻で笑う。「ほら、こいつも言ってるだろ? 出てけよ」
「お願い。もう出て行ってほしいの、烈久」
はっきりとそう言った。小声ながらも芯の通った声だった。その裏側に彼女の決意と勇気をうかがい知ることができた。途端に男のマスクがひび割れ、そこから歪んだ形相が現れた。眼光はジャックナイフのようにぎらつき、口元の皺は底なしの谷のように深かった。一心不乱に彼女を蹴りつける。洋一は体当たりして男をベッドへと押し倒した。揉み合いになりながら男の拳が腹に数発叩き込まれる。内臓を抉られるような痛みが襲った。腹を抱え退く。液体が喉から口へと逆流する。ハンカチでぬぐうと不快な臭いが鼻にこびりついた。
背筋を伸ばし洋一は眼鏡を上げた。「あなたには花岡さんと交際する資格はありません」
風で揺らぐ蝋燭の燈火のように男はゆらりとベッドから起き上がった。
「あなたが本当に……本当に花岡さんを愛しているなら、こんな風に傷つけたりはしません」
初めて耳にする言葉みたいに「愛?」と男は呟き、足を踏み出した。憎悪の炎を宿した目が迫り寄る。「お前みたいな奴、反吐が出るんだよ」
男の拳が振り上げられた瞬間、ガラスの砕ける音がし視界が真っ暗になった。目玉の奥が熱い。まるで右目を熱した針で突き刺されたようだ。状況を把握する間もなく、硬球が顔面に炸裂したかの痛みが走る。何度とあびせられ、耐えきれずに膝をついた時、百永美の声が耳を劈いた。
「やめて!」
左目を何とかこじ開けると、眼鏡がひび割れ、その亀裂の向こうで百永美が必死に男の片脚にしがみついていた。離せよ、と男は煙草の火でも揉み消すように彼女の腕を踏みにじる。彼女は嗄れた叫び声を上げながらも決してその手は離さない。
気がつくと洋一は手を振り上げていた。
掌で爆竹が弾けたような音がした。男の頬は赤く染まり、少年みたいに澄んだ瞳を洋一に向けていた。僕なぜ叩かれたの、そう訴えられている気がした。この男はどんな境遇で生きてきたのだろうか、幼い頃に暴力を注意する大人が周りにいたのだろうか。
百永美の気持ちが理解できた。ほんの少しだけ。
「哀しい人だ」洋一は錆臭く粘ついた舌触りを感じながら口を開いた。
「なんだ?」
少年のまなざしは影を潜め、ぎらついた眼光となっていた。
「あなたは哀しい人だ、と言ったのです。過去に何があったのか知りませんよ。家族に愛されなかったのかもしれません、不当な暴力を受けてきたのかもしれません、周りから蔑まれてきたのかもしれません。あなたを取り巻いていた環境が力を行使することでしか 自己表現できない、もしくはそれが唯一生きる術だと学び育ってきたのでしょう、それはね、わからないでもない。しかしながら! そのようなことが哀しいのではありません。過去に囚われるばかりで今傍にいるのは誰なのか、今大切にしなければいけないのは誰なのか、それをわからないことが哀しいと言ってい……」
強烈な膝蹴りが腹に捻じ込まれる。が、洋一は踏ん張った。
「力で捻じ伏せることが真の強さでしょうか? 僕にはね、あなたが怯える小猫にしか思えません。土砂降りの中、ダンボール箱で凍えている子猫、花岡さんが手を差し伸べているにもかかわらず怖がって爪を立てる小猫と一緒です。怖いのですか? なにを怯えているのです? 人に優しくされるのが怖いのですか。優しさにふれ、温かみを憶え、心を許した後に突き放されるのが怖いのですか。勇気があれば素晴らしい恋愛ができるというのに目を背けるばかりだ。一体全体あなたは、なにを待っているのです? 暴力をも受容して全てを包み込んでほしいのでしょうか。甘い! 甘々ですよ! あなたはもう充分な大人なのです。人を愛する勇気をお持ちなさい」
洋一が訴える中、男の攻撃が容赦なく降り注いでいた。踏ん張っていたはずなのに、いつの間にやらサナギのように蹲り、身を固めている。
「やめて、死んじゃう」
遥か彼方から叫んでいるように百永美の声がやけに遠退いて聞こえた。立ち上がる体力も気力もない。顔を上げるのが精一杯だった。巨人のように男が見下している。
「弱いくせに粋がってんじゃねえよ」
そう言って、洋一の頬に唾を吐き捨てた。
怒りも屈辱感も湧き起こらなかった。どうやら限界に達しているみたいだ。意識が朦朧とする。突然床が抜け、落下していく。深く深く地の底に近づくにつれ、痛みは緩和し、むしろ空を飛んでいるかのように心地よくなる。ゆったりと辺りを見まわすと、そこは光の存在を許さない闇そのものだった。しだいに身体がふやけ、闇と同化したかの気分となる。このまま身を委ねようじゃないか。きっと楽になれるはずだ。
――おかえんなさい、ラブマネさん。
気がつくとアパートの玄関に佇んでいた。愛子が歩み寄る。心身ともにくたびれていたものの、出て行ったはずの彼女が戻って来たことに安堵する。とびきりの笑顔は待ちわびた夜明けのように眩しかった。
――どうしたの、その怪我?
洋一の頬と唇のちょうど中間あたりの傷口に手を添え、まるで我が身にふりかかった出来事のように愛子は眉間に皺を寄せた。
「ああ、仕事でね。それよりもこんな遅くまで起きてたのかい?」
――待ってたの。洋一こそ大変だったね。
「しかし救うことができなかった。そればかりか僕が不甲斐ないせいで事態は悪化した」
――そんなことないよ。洋一は立派に支援してるじゃない。
「きっと僕には向いていなかったんだ。自分の恋愛も満足にできないのにね。以前キミが言った通りだよ」
彼女は肯定とも否定ともとれない複雑な顔つきをした。
「もう辞めようと思うんだ」
――そっか。
「きっとその方がいい。キミもそう思うだろう」
――洋一が決めたことなら、それでいいんじゃないかな。でも……
「でも?」
――まだ終わってないよ。
「なにを言ってるんだい。僕にはどうにもできなかった、だからこうして帰宅しているんだよ」
――さあ、そろそろ戻らなきゃ。
「もうくたくたなんだ。少し休ませてくれ」
――ダメ。辞めるのは自由だけどね、まだ終わってないの。
「どうして? どうしてそんなこと言うんだ」
――ドシテドシテ虫!
「なんだよ、それ」
――聞こえるでしょ、彼女の悲鳴が。百永美さんはまだ助けを求めてる。
「残念ながらもう身体が動かない。こうやって立っているのが精一杯だ」
――諦めないで。だって洋一は……でしょ?
「なんだって? 聞こえないよ。もう一度言ってくれ」
愛子は深く頷くと、玄関から押し出すように胸を叩いた。
――いってらっしゃい。
身体が引き裂かれるかの激流にもまれ、眠りの深淵から目を醒ました。どのくらいの時間かわからないが気を失っていたようだ。頭を振子みたいに揺らし、立っている。ふらつく頭を止めようと試みるが、止まるのは一瞬で、逆に反動がかかり転倒しそうになった。
「なんだよ、ぶつぶつと独り言かよ。気持ち悪りいな」男は言った。
夢を見ていた、愛子の。
「今、夢を見ていました。夢の中で語りかけてきた彼女に違和感がありました。なんだか、脇腹をくすぐられるようにむず痒いです。違和感ですか? そうですね……彼女があのように親身に僕の話を聞くことはないし、もう少し無関心、というか大雑把なのです。理想が入りまじって脚色されていたのでしょうかね。おそらく現実の彼女ならば大怪我して帰宅しようが、帰り道で転んだくらいにしか思わないでしょう。ふ、ふ、ふ!」口元が自然と綻ぶ。「え? なにがおかしいのか、ですって? 勘違いなさらないでください。自虐的な意味合いで笑っているわけではありませんよ。気づけたことが嬉しかったのです。理想と現実のギャップなんて実に些細なことではないか、と。心の奥底で僕は彼女に出会えたことで、いつもすぐ傍で見守り、支えてくれていたことに気づけたのですよ、ようやくね」
「なんだよ。ラリってんのか」
男が狼狽して見えた。
「あなた言いましたよね。弱いくせに粋がってんじゃねえよ、と。一語一句間違いはありませんね。ええ、仰る通り僕は弱いです。この世に生を受け二十三年間、喧嘩と呼べる喧嘩は一度だってろくにしたことがない、恥ずかしながら。僕が弱いため彼女を哀しませることも多々ある。トイレットペーパーが床に垂れているだけで苛々したり、放屁することだって笑って許してあげられない。十人十色、千差万別、価値観やものの考え方は違う。当然ですよ、人間ですもの。全く、心の狭い男ですよ僕は。先日もね、彼女が僕の知らない男にハンバーグを作ったことに、嫉妬し、怒鳴ってしまったのです。それが発端となり彼女はアパートから出て行ってしまった。彼女がどうしてそのような思いに駆られたのかを考えようとしなかった。しかし今ならわかる。僕とわかり合えないこと、僕が彼女を理解しようとしなかったこと、それがつらかったんです。誰かに寄り添いたかった。本来僕でなければならないのに突き放してしまった。ふう。この通り弱いことを自覚しました。ところで、あなたはどうですか。僕より優っているのでしょうか? 残念ながらそうは思えませんね。正直負ける気がしないのですよ。いくら虚勢を張ってもあなたの心はいつも独りぼっちだ。それに比べ僕の心は彼女で満たされている。負けるわけがない!」
百永美を背に洋一は両手を広げた。
「僕は花岡さんの恋愛支援専門員ですから。必ず救いますから」
男が殴りかかってきた。洋一はじっと耐えた。彼女に被害が及ばぬよう耐え続けた。
そして洋一は見た。
夢か幻か、何者かが颯爽と現れ、男を取り押さえる姿を。
瞼を開くと、曇り空のようにどんよりとした灰色に覆われていた。洋一はベッドに横たわっている。天井から視線を逸らすと、パイプ椅子で男が脚を組みながら新聞を広げていた。誰だろう、彼が助けてくれたのか。
全身の痛みを我慢しながら起き上がり、「眼鏡……眼鏡」と、ゾンビのように腕を伸ばした。
彼は新聞を伏せ「ああ良かった。眼鏡はここにあるよ。ひどい有様だが」と差し出した。
ひび割れた眼鏡を嵌める。目の前にいたのは四谷所長だった。
「所長……」洋一は意外な人物に驚きながら呟いた。「え、ここはどこでしょうか? もしや、また夢? ということは、所長も僕の心の奥底で支えてくれる存在なのですか」
「病院だよ。大丈夫かい? 頭を強く打ってるらしいからね。けれど、検査結果は異常なかったから安心したまえ。脳も骨も問題なしだ。外見は眼鏡と同様ひどい有様だが入院するほどでもない」
周りを眺めた。多床室なのだろう、カーテンで仕切られている。物といえば、ランプ付きの台にテレビが置かれているのと、隅にクローゼットがあるだけの簡素な造りだった。窓からは薄闇がかった空と木々が見える。早朝なのか夕時なのか判別がつかない。
「今、何時ですか?」
四谷所長はテレビで隠れていた掌サイズの時計を移動させ、「六時半だ、午後のね」と言った。
午後の六時半、そんなに長い間気を失っていたのか。ぼんやりとする頭に、ひらりと百永美の顔が舞い降りた。
「花岡さんはどうなったのですか」
「ここに運ばれて別室で休んでいるよ。骨折はあるが命に別状はない。意識も戻っている。当然、彼女はしばらく入院となるそうだが」
そう言うと四谷所長は両膝に手を添えた。枯れ木のように痩せ細った手だった。
「所長が助けてくれたのですね」
「まさか、警察だよ」
「でも所長が呼んでくれたのですよね。ご迷惑おかけしました」
四谷所長は薄らと伸びた顎髭を撫でた。「富樫は警察署で事情聴取を受けているところだ。納得がいかないと暴れているそうだがね」
富樫……百永美の交際相手の名前だったはずだ。
「おそらく注意で済んでしまうのでしょうね。富樫さんが警察から解放された後のことを考えると不安でなりません。彼女は一体どうなってしまうのでしょうか」
「報復は警戒せねばならんね。脅すわけではないけど影沼くんも他人事ではないよ」
不吉な影が背後へと這い寄る気がした。
「当面は手出しできないよう手配はしてある」
「手配?」
「花岡さんは退院できしだいシェルターで隔離されることになる。今のアパートに戻るのは非常に危険だからね。ほとぼりが冷めるまで保護してもらうしかない」
安堵の息が洩れる一方、四谷所長に対して後ろめたい気持ちとなった。
互いに沈黙し、カーテンの向こうから看護師と患者の話し声が聞こえてくる。蛍光灯に光が灯ると四谷所長は思い出したように口を開いた。
「なあ、どうして相談してくれなかったんだい?」
穏やかな口調に反して刺すような彼の視線に驚いた。過ちを咎めるような厳しいまなざしに、洋一はうつむく。どうして相談しなかった? 四谷所長に相談しても無駄だと思ったから。頼りにならなかったから。そうだろう?
「花岡さんが虐待されていたことは気づいていたんだろう。彼女の部屋にはDV防止のパンフレットがあった。今回、それを富樫が発見したことが原因だったそうだよ。パンフレット……影沼くんが渡したんじゃないのかな」
噎せ返るほどの重圧がのしかかる。スローモーションで崩れてきた瓦礫に頭上から押し潰されるように頷き、シーツをぐっと握りしめた。何日間とオアシスを探し求め、砂漠を歩き続けたかのように喉元が枯渇する。
「勘違いしないでくれ。影沼くんの対応が悪かったとは思わない。むしろ、管理が甘かった私に責任がある。こんな怪我までさせてすまなかった」
こんな自分に頭を下げないでくれ、そう思った。
四谷所長は顔を上げ、すうと息を吐いた。「ただ……この事実を受け止めてほしかったんだ。影沼くんが虐待に気づいた時点で私に相談し、緊急隔離に踏み切っていたとしたら花岡さんはこんな目に合わなかった。もちろん影沼くん自身もね。恋愛に法則なんて存在しない。マニュアル通りにいかないのが常だ。二十四時間抱き合っていたい日もあれば、顔を見るだけでうんざりする日だってある。相手に対して不満なく心が満たされている人なんて一握り。大半は不満を抱いているんだよ。そんな不安定な利用者を私たちは支援している。なにが正しくて、なにが誤りなのか、一ノ瀬くんにしろ六本木くんにしろ、悩みながら支援しているんだ。私だってそう、みんなそうなんだよ。ひたすら悩んで、それでも上手くいかなくて、それを繰り返しつつ、ゆっくりと前進していく。事務所に座っているだけだとそれぞれの苦悩は見えないだろうけど、みんな経験してきたんだ。一人悩むのも大いに結構、失敗するのも大いに結構、だがね……それはケースによる。今回に限っては相談するべきだった。そのために私たち上司がいるんだ。結果論だと思うかい? しかしね、取り返しのつかないこともあることを理解したまえ。今年入社したばかりの影沼くんよりは、少なくとも経験も知識も豊富だ。アドバイスもできた。未然に防ぐこともできた。もっと人の意見に耳を傾けるべきだった」
四谷所長の言う通りだ。自らの過ちに心を痛めながらも、彼の一言一言に温かみを感じとっていた。ふと、父の姿と重なった。我が子を見失わぬように、手をとって歩いたあの日の父は、確かに父親だった。いつもよりずっと大きく、誇らしかった。
「申し訳ありませんでした」
洋一は自然と口が開いていた。
「責めてるわけじゃないんだよ」
「違います。僕、ずっと所長のこと……所長のことナメていました。見下していたのです」
「知っていたさ」
くしゃりと鼻口を寄せて笑う彼に、洋一は意表を突かれた。
「内心でナマケモノだとか、ミステリーサークルみたいな髪型だと思っていたこと、全て見抜かれていたのですね」
「え? そうだったの。それは少しショックだなあ。でもまあ、まだ若いんだ。何事も経験だよ。これからたくさんの人と接していくに従って、内面を見る目がしだいに養われるさ。そんなこと言って、内面を知ると今よりもっと見下させるかもしれんがね」四谷所長は窓際に立ち、故郷の情景と想い重ねるように暮れゆく景色を眺めた。「影沼くんはね、私の誇りなんだ。ひとつひとつ指示しなくても、自分で考え、自分で学ぶ。努力家で熱意だってある。なによりもラブマネにとって必要な人を想いやる心を持っている。恋愛は人を強くする反面、臆病にすることもある。弱さや脆さを受け止め、支えることができる、影沼くんはそんな強い人間だ。これからもより良い支援ができる、そう信じているんだよ」
熱くなる目頭を洋一は指で押さえつけた。やめてくれよ、柄にもない。すると今度は鼻水が溢れ出てくる。勘弁してくれよ、みっともない。
「どうして……どうしてそのようなこと言うのですか。僕のせいで花岡さんを余計に傷つけてしまった。恋愛支援専門員を続けていく資格はないと思っていた。しかし、そんなこと言われたら僕は一体どうすればいいのですか」
「辞める必要なんてないさ」すまなそうに唇の端を持ち上げた。「さっき言いそびれたんだがね、実は彼女を救ったのは影沼くんなんだよ。事務所でカルテを探してと手間取ってしまって、僕が電話した時すでに警察は通報を受けた後だった」
「僕ではありません。携帯電話は蹴り飛ばされ連絡できなかったのです」
「不審に思った近隣住民から通報があったんだ。変質者が押し入り喚き声を上げているってね」
洋一は笑うしかなかった。「変質者、僕のことでしょうか」
「結果的に影沼くんが花岡さんを救った、これに間違いはない。さっきは厳しいことを言ったがね、影沼くんがラブマネとして関わっていたからこの程度で済んだとも考えられる。矛盾することを言うが、もっと重症になったかもしれないし、もしかしたら花岡さんは生命を奪われていたかもしれない。ほら、氷山の一角と言うだろう。目に見える氷山を大きな事故に例えるなら海面の下には二十九の事故が潜んでいる。事故は起こってしまったが、影沼くんのおかげで明るみとなり、将来起き得る可能性があった最悪の事態は免れた」
「ハーバー・ウィリアム・ハインリッヒの傷害四角錐ですね」
「あ、ああ、そう。バーバー……ウリウリリッヒ」四谷所長は首筋を掻いた。「前言撤回するよ。知識は影沼くんに及ばない」再びパイプ椅子に腰掛け、「動けるかね? 話はこのへんにして彼女の傍にいってあげなさい」と言った。
戸惑っていると「彼女のラブマネだろう」と後押しされる。洋一は頷き、足を床につけた。痛みが全身に響くものの歩けないほどではない。
隣の病室で百永美は横になっていた。悲惨なくらい顔が青紫に腫れ上がり、全身包帯で巻かれ、右脚はギプスで固定されている。
「すみません。僕がパンフレットを渡したばかりにこんなことになってしまって」
深々と頭を下げる洋一を一瞥し、彼女は溜息をついた。「影沼さんみたいなお人好し初めて。鏡見ましたか? 私のこと心配できないくらい腫れていますよ」
痛みを我慢しながら顔面にふれると、確かに特殊メイクを施されたようにデコボコと盛り上がっていた。
「夜中に呼び出されて、そんな酷い目に合わされて馬鹿みたい。赤の他人のために、なんでそこまでするのかわからない」
「赤の他人ではありません」
苛立った口調で「ええ、ラブマネでしたね」と言うものの、すぐさま後悔を噛みしめ「すみません」とうつむいた。
「退院後のことは聞いていますか?」
「はい、さきほど四谷さんから。保護施設で過ごすように、と。落ち着いたら引っ越しするようにも勧められました。警察も同行してくれるからって」
「その方が安心です」
「ありがとうございました、なにからなにまで」
「僕はなにひとつやっていません。所長が全て手配してくれたんです」
「でも、影沼さんは助けに来てくれた」彼女は拳を見つめながら言った。何か握っている。隙間から朱色が覗いていた。「この御守に見憶えがあるって言ってましたよね」
血に染まった蜻蛉新社の御守であることに気がつき、「ええ」と頷いた。
「十年ほど前……元旦に、蜻蛉神社で女の子を助けませんでしたか? 小学生くらいの」
中学の頃だったか、父と訪れた初詣の光景が脳裏に蘇る。今にも溢れ出しそうなほど涙を溜めた瞳、家族と再会でき綻んだ口元。そうだ。あの日、女の子だったか定かでないが子どもを助けた記憶があった。
「もしかして、あの時の」
「やっぱり」彼女は全て悟ったかのように顎を引いた。「影沼さんに助けてもらったの、これで二回目なんですね」
テレビ台に置かれたバッグが震えた。災厄が過ぎ去るのを祈るかのように百永美は瞼を閉じて身を強張らした。
「失礼します」洋一はバッグから彼女の携帯電話を取り出すと電源を落とした。「電話持ってきて良かったです」
「学生証や携帯電話は悪用されるといけないからって、四谷さんがまとめてくださったんです」彼女は怯えながら訊ねた。「誰からですか」
「単なるダイレクトメールです。気にすることはありません、番号は替えればいいのです」
なおも強く御守を握り続け、彼女の手は燃えるように真っ赤になっていた。「私を助けてくれたのはラブマネだからですか」
「もちろん」
頷く洋一に包帯でぐるぐる巻きの腕を伸ばし、百永美はすがりついた。
「私、怖いんです」
ざらついた包帯の感触と掌の熱感が伝わる。
「大丈夫です」
「お願い。傍にいてほしいの」
「傍にいますよ。僕はあなたの……」
「恋愛支援専門員だから?」彼女はゆっくりと首を振る。「違う。ラブマネとしてじゃなく傍にいてほしいの……影沼さんにいてほしいの」
「どういう意味でしょうか」
「好きだったんです。信じられないと思うけど、あの日から……神社で助けてもらってからずっと」
「思い出は美化されます。それに今は精神的に弱っている」
「そんなの関係ありません。精神的に弱っているからこそ影沼さんを頼っているの。おかしいですか? こんな時に告白するなんてずるいのはわかってます。でも……傍にいてほしいの。ずっと好きだったの。運命の人だって信じてるの」
潤んだまなざしに吸い込まれ、無意識に肩を抱き寄せていた。すると乱れていた呼吸が規則的となり、肩の力がほぐれ、彼女の安心感を肌で感じとることができた。
洋一は瞼を閉じ、愛子を想い描く。
「僕、同棲している彼女がいるのです」そう言って百永美の身体をそっと引き離した。「厳密には先日喧嘩となりアパートを出て行きましたがね。彼女はね、ひどいぐうたら者なのです。朝寝坊なんて日常茶飯事、ボジラの目覚まし時計を買ってきたのですが全く効果なし。大音量の咆哮をものともせず、すやすや眠りこけています。ようやく起きてきたかと思えば、丹精込めて作った朝食を一瞬で平らげてしまうのです。ゴミ収集車の如くね。食器の片づけだってろくにしない。食べたら放ったらかし。掃除も洗濯も炊事も僕が全てこなしている。彼女は、ありがとうの一言を言えばそれでいいと思ってふんぞり返っているのです」
「男の人でそこまでしてくれる人いないですよ。私は料理得意だし、家事もする。影沼さんにそんな思いさせない」
「そんな彼女に苛々して小言を洩らしますが聞いているのかいないのかケロっとしています。稀に料理をやったかと思えば、これがまた目もあてられない出来栄えなのです。フライパンは油が残ったままだし真っ黒に焦がす。二年はもつペラピットを、ですよ」
「私は大切に扱うわ」
「さらに彼女は下品極まりない。僕の目の前で平然と放屁するのです。恥じらいなんてあったものじゃない」
「信じられない」
洋一はズボンからリストバンドを出し、突きつけた。「これ見てください。僕に似合うはずないのに贈ってきたのですよ、記念日に」
「私ならもっと素敵な物をプレゼントする」
「夜遅くまで残業して、くたくたになって帰宅すれば、まるで強盗に荒らされたように部屋中が散乱している。夕飯なんてカップラーメンがぽつねんと置いてあるだけです。それでもって彼女は平気な顔で、おかえんなさいって言い寝床に就いてしまうんです……でもね」洋一はすっと息をのんだ。「朝彼女がいないとなにか物足りない気分になるのです。寝起きの悪い彼女と格闘することは大変ですが賑やかでした。先月『マンナンウォーズ』へ食事に出かけたのですが、勢いよく平らげる彼女を見ていて、不思議と気持ちが良かった。僕なんて食が細いからチビチビとしか食べませんからね。彼女は細かいことは気にしない、いつだっておおらかなんです。僕なんてトイレットペーパーが替えてないだの、水滴が飛び散っているだの口を開けば小言ばかりだ。目の前で放屁するのもきっと僕に気を許している証拠なんです。僕なんて恥ずかしいことを理由に、彼女の前で放屁ひとつする勇気もない。このリストバンドだって、忘れっぽい彼女が……記念日を憶えていてくれたんです。それに引き換え、僕はどうでもいいことばかり憶えているのに、肝心な記念日をすっかりと忘れていた。そんな僕に……残業が疲れたからって不機嫌な顔して帰ってきた僕に、おかえんなさいの一言を言うために彼女は待っていてくれている。彼女とは大学時代に食事会で知り合いました。俗にいう合コンです。運命の出会いとはほど遠いですけど、僕は彼女の……愛子の傍にいたいんです」
百永美はうつむき、小刻みに身体を震わせていた。
「だから申し訳ございません」洋一は背筋を伸ばし、頭を下げた。
笑い声が室内に響いた。
しゃっくりを連発するようにして「どれだけ好きなんですか。呆れちゃいますよ」と百永美は言った。「もしかして、私が本気で告白してると思ったんですか? 冗談ですよ。冗談に決まってるじゃないですか」
彼女は瞳を真っ赤に充血させ涙を浮かべている。
「やだ、涙が出てきた。影沼さんが笑わせるからですよ」
「申し訳ございません」
「謝んないでください。ああ、もう涙が止まらないじゃない」
嗚咽交じりの笑いを見守っていると、彼女は息を整え「もう帰って。私ならもう大丈夫ですから」と言った。
「しかし」
「いくらラブマネだからって、これ以上優しくするのはずるいです」
洋一は納得して退室しかけると百永美が呼び止めた。手首をツンツンと指し示している。「リストバンド嵌めたらどうですか? 案外似合うかもしれませんよ」
洋一は笑って頷いた。
『おかえんなさい、ラブマネさん』その11へ続く