こんにちは、宮比ひとしです。
この記事では、オリジナル小説である『おかえんなさい、ラブマネさん』その4を紹介します。
恋愛支援専門員(通称ラブマネージャー)である青年が、個性豊かな利用者の恋愛支援に奮闘するラブコメ小説となっています。



おかえんなさい、ラブマネさん その4
十月二十八日 金曜日
トイレへ行き、洗面台で顔を洗い、テレビの電源をつける。いつもと何ら変わりのない朝を迎えた。トーストにバターを塗りながら愛子は何時に帰ってきたのだろう、と思った。テレビ音に負けじと愛子はいびきをかいている。
ジャケットを羽織り、寝室を覗く。例の如く彼女はぺしゃんこになった蛙のポーズで熟睡していた。カレンダーの二十八日には赤と黒の丸がついている。本来なら久々に二人そろっての休日だったが、仕事が入ってしまったので仕方ない。まあ、別段に予定を立てていた訳でもないのでいいだろう。愛子を敢えて起こすのも忍びなかったので、メモ用紙に「仕事になりました」とだけ書いて朝食の皿に敷いておいた。これで充分伝わるだろう。
事務所で挨拶を交わし、鞄に書類を詰め込むと自転車に跨った。矛差乃山へ向けての、なだらかな傾斜路を進む。この地区は地主が多く、門構えの日本家屋が建ち並んでいる。とりわけて立派な木製の門を前に見上げると表札には稲妻が走ったような字で濱崎とあった。門を潜り、自転車をその裏に停めた。
石畳の通路が母屋まで伸び、その脇には訓練のいき届いた兵隊が背を反らして敬礼するように松がずらりと植わっていた。いそいそと屈みつつ通過し、玄関口にあるインターホンを鳴らす。
しばらくして戸が開いた。ブラウスに紺のカーディガンを纏った女性が「お待ちしておりました」と、うつむきがちに視線を送る。「どうぞ、お入りくださいませ」
濱崎の妻である弘子は端整な顔立ちであった。目尻や口元には五十代半ばの年相応といえる皺が刻まれているものの、それもまた魅力の一部となっている。そして、美人特有のすました雰囲気を醸し出していた。愛想がないともいえる。毎度のことだが無言で導かれる廊下がやけに長く感じられた。
襖を開くと、そこは庭が一望できる眺めの良い和室だった。どっしりとした木製の長机に座布団が二つある。
「どうぞ、おかけになってくださいまし」
座布団の脇に座ると、弘子は表情を崩すことなく機械的に「座布団におかけください」と促した。彼女に言われるまま埋もれるくらいふかふかな座布団に正座した。
「詳しいことはうかがっていませんが、また主人が無茶を言ったそうで申し訳ございません」弘子は深々とお辞儀する。
「いえ。私の責任ですから」
「只今、主人を呼んで参ります」
彼女が引き下がると、水のせせらぎが聞こえてきた。庭の池では鯉が大儀そうに泳いでいた。ときおり鹿威しが趣のある音をたてる。咳払いとともに濱崎は現れ、どかりと座布団に胡坐をかいた。白髪に四角い輪郭、眉毛のうねり具合、気難しい顔を絵に描いたような顔つきだ。ハガキらしきものを手にしている。
「先日は旅行会社まで足を運ばれたのに、私の不注意で大変失礼しました」
「しっかり仕事してもらわないと困るよ、影沼くん。私たちの税金から給料貰っているんだろう。違うのかね」口をへの字にひん曲げ、腕組する。
急速に喉が乾いていく。軽い吐き気が襲う。鬼瓦のような形相で睨みつける濱崎にただ頭を伏せることしかできなかった。
「まあいい」腕をほどくと、手にしていたものを机に突き出した。
恋愛保険証だ。
洋一は拷問から解放された面持ちとなり、鞄から更新届を出した。被保険者番号や事業所情報はすでに記入してあるので、後は濱崎のサインと印鑑を貰うだけだ。内容に目を通すと彼は胸元に差していた万年筆のキャップを抜く。紙に穴が空いてしまうのではと心配になるほどの力強いサインだった。
受け取ると、「どちらへ旅行される予定ですか?」と、安心したせいかしら自然と言葉にしていた。
彼の眉間に皺が寄る。そんなことは関係ないだろう、そう怒られるのではと身を竦ませると、彼は「静かに」と廊下へと注意を払った。
弘子は控えめに座敷へと上がり、盆にのせた緑茶を差し出した。その間、濱崎の目は洋一を離さなかった。迂闊に喋るんじゃない、そう目で訴えていた。頭によからぬ疑惑が生じる。もしかして彼は浮気をしているのではないか、妻に黙って別の女性との旅行を企てているのではないか。特定の異性や家族以外との旅行でなければ恋愛保険は適用されない。違反行為にあたるのだ。場合によっては担当する恋愛支援専門員にも罰則が与えられる可能性がある。洋一は身構えた。
弘子の足音が遠ざかっていく。
途端に濱崎の頬が綻んだ。鹿威しの音を追うように庭園を見やり「伊豆だよ」と目尻に皺を寄せて言った。「私は仕事一筋でね。家内とは新婚旅行で伊豆へ行ったきり、長年、どこへも連れていくことができなかった。それに一人娘も就職し家を出て行ったからね。寂しい思いをしているんじゃないか、とね。家内には内緒で計画してるんだよ」
照れくさそうににやける彼に胸が温かくなった。
「温泉ですか。奥様きっと喜ばれますよ!」
「そうだといいがね」
濱崎は高らかに笑い声を上げた。
市役所に更新届を提出し、やれやれと猪頭公園についたのは午後の一時半だった。ようやく昼飯にありつける。ベンチに腰を掛け、鞄を開けると携帯電話のライトが点滅していた。愛子からメールが来ている。
『今日シゴトになったの?』
『保険の手続きが入ってしまった。僕の不手際ではあるけれど、その利用者がクレーマーのようで散々だったよ。』と返信し、弁当を頬張りながら労いを期待してみるものの、彼女からの返事は『そうなんだ。』の一文だけだった。
携帯電話をベンチに放る。いつだって彼女はそうだ。いくら汗水垂らし帰宅しようが、遅くまで残業しようがお構いなし。おかえんなさい、いつもそれだけだ。
携帯電話がカタカタと振動する。愛子からだろうかと手に取るが画面には美鷹恋愛支援センターと表示されていた。何かあったのか。通話ボタンを押した。
『今なにしてるの?』
声の主は一ノ瀬だった。
市役所の帰りに休憩していることを伝える。
『大空夏樹さんってヨウくんの担当だったよね。事務所に電話がしきりにかかってきて大変なの。彼女の電話番号言うから至急かけてちょうだい』
返事も待たずに一ノ瀬は番号を口にするので慌てて手帳に書き留めた。
『すぐにかけてちょうだいね』と念押しして電話を切った。
恨めしげに三分の一も食べていない弁当に蓋をし、メモした番号に電話をかける。すぐさま繋がった。
もしもし、と受話口から聞こえる夏樹の声は明らかに苛立っていた。
「恋愛支援専門員の影沼です。事務所に何度もお電話……」
『遅い! もうわたし彼と別れることにしたから。今すぐ解約の手続きして』
ふざけるな、勝手に決めるなと奥で男が怒鳴っている。
『なにすん……邪魔しな……』
揉み合っているのか言葉が途切れ途切れとなる。どうやら彼氏と喧嘩でもしたのか別れ話へ発展しているようだ。
「落ち着いてください」
洋一は声を張るが、互いの悲鳴やら罵詈雑言が入り乱れ、とても会話できる状況ではない。何度か通話口に向かって訴えてみるものの効果は全くなかった。しだいに喉が痛くなり、よくもまあこれほど罵り合えるものだなと諦めた直後、静寂は訪れた。
洋一はホッとした。「大空さん、話を聞かせてください」
ゴトゴトと不吉な物音が耳元に響く。
『おい……よせ』
男に先ほどの威勢はなく随分と怯えた声色だった。
『包丁なんか持ってどうするんだ』
洋一の顔面から血の気が失われていくのを感じた。無情にも野太い叫び声と同時に通話は途絶えた。即座にリダイヤルを試みるが陽気なメロディコールが流れるだけだ。
「冗談じゃない」
自転車のペダルを踏みしめ、夏樹のアパートへと全力疾走した。
ドアを前にすると顔も知らぬ夏樹の彼氏が血塗れで横たわっている姿が脳裏に浮かんだ。それを払拭するようにインターホンを連打し、ノックしては彼女の名を呼び続けるが反応はない。ごくりと生唾をのみ込み、ドアノブをまわす。鍵は掛かっていなかった。覗きながら「影沼です。大空さん、おじゃましますよ」と言う。自分でもビックリするくらいに甲高い声だった。
返事はなかった。そろりそろりと忍び足で玄関を進む。もしかすると、あの遣り取りは彼氏の家での出来事だったのか。そうだとすれば万事休す打つ手なし、そう思った最中、男の呻き声が地鳴のように響いてきた。心臓が跳ね上がる。反射的にリビングへ駆け出すと、うつ伏せになった大男に夏樹が跨っていた。
「やめてくれ」男の顔は悲痛から歪み、全身を痙攣させていた。
躊躇することなく彼女は上半身を傾け、両手を背中に押しつける。その手には包丁の柄のようなものが握られていた。悶え苦しむ男を見下しながらワニのイヤリングを揺らし冷徹に微笑する彼女に身の毛がよだった。
「な、なにをしてるのですか」
洋一は後ろから羽交い絞めにすると、「なんであんたがいんの。離してよ」とポニーテールを振り乱し暴れる。バランスを崩し二人もろとも尻餅をついた。「もう! 痛いじゃない。なにすんの」
「それは僕のセリフです。自分がなにをしでかしたか、わかっているんですか」
彼女は呆然としていた。力強い訴えが心に刺さったか。いや、今はそれどころではない。男の救命を優先せねば。
「大丈夫ですか! 今救急車を呼びますから」
男はむっくりと起き上がり、視界を遮る。悲痛な表情はどこへやら仁王像の如く堂々と立ちはだかる。洋一はあまりの上背に海老反りとなって見上げた。
「大丈夫……ですね。救急車は」
男の分厚い唇が震える。「一体なんだ? 断りなく勝手に上がって、あろうことナツを押し倒しやがって」張り裂けんばかりのタンクトップと胸板がぴくんぴくんと上下する。首、肩と回転させ骨を鳴らす。「覚悟は出来てるんだよな」
「僕はですね、あなたを助けようと……」
弁明しかけ、夏樹の持ったそれが目に留まった。なんとそれは、旅館の土産売場でよく見かけるツボ押し棒だった。頭を抱えずにはいられなかった。
「今頃、後悔しても遅いんだよ」男が拳を振り上げた。
「ストップ、コウちゃん!」夏樹の声が矢となり男を射抜いた。ピタリと制止する男に「どーどー。落ち着いてそこ座りなさいよ」と猛獣使いのようになだめ、彼もまた飼いならされた猛獣のように従った。
「この人はわたしのラブマネの長沼孝七」
「影沼洋一です」冷汗をハンカチでぬぐい、会釈する。
「で、こっちが坂本浩介。わたしの彼氏」
「なんだよ。てっきり強盗かと思ったじゃねえか」誤解がとけるや浩介は豪快に笑う。「ちゃんとインターホンあるんだから鳴らしてくれよな」
「鳴らしましたけど」洋一は眼鏡をくいっと上げる。
「一回じゃ気づかねえって」
「何度も押しましたけど」眼鏡をくいくいっと上げる。
冷蔵庫を開き、夏樹は「あ、今壊れてるの」とあっさり言った。「いつまでも突っ立てないでそこに座れや」浩介が卓袱台を寄せるので座ると、なみなみに注がれた黄色のジュースがドンと置かれた。水面が静まるのを見守っていると、二人は躊躇いなく飲み干し「パイナップルは美容にいいの」「パイナップルは栄養満点だ」と重なる声に、お互い見つめ合いヘラヘラと笑う。
なんなのだ、この二人は。
零さぬようにゆっくりとジュースを啜り、目を瞠った。なんたる美味。パイナポー独特のトロピカーナな甘みが舌に絡み、血液がフラダンスを踊るかの活力みなぎり、グラサン太陽に燦々と照らされているみたいに身体中が火照って……嗚呼、ここで一句。
夏樹浩介の空グラス 諸行無常の響きあり
バーミリオンの鼻の色 盛酒必酔の理をあらわす
枠笊人も久しからず
ただ南の陽の夢の如し
「って! これお酒じゃないですか」
「そうよ。ジン割り。ウマいでしょ」
「美味しいです」ぶるぶると首を振る。「いや、美味しいですけれども! 僕仕事中なんですよ」
「そんな小さいこと気にしちゃダメよ」彼女は浩介のグラスに注ぎ足した。
「それに大空さん未成年でしょう」
「わたしのはアルコール抜きよ」
「噂どおりだな。ヌマッチ」タラコ唇をぱっくり開き、浩介は二杯目を流し込む。
「ヌマッチ……? まさか僕のことですか」
「他に誰がいるのよ」
「しょっちゅう愚痴聞かされてるよ。細かいこと言って、あんまりオレやナツを困らせないでくれよな」
彼は酔っ払ってるのか陽気に笑い、グローブのような手で何度も肩を叩いてきた。二キロの米袋が圧しかかってくるほどの衝撃だ。眉を顰めながらも頷いていると、「ヌマッチ。急になにしに来たわけ?」と夏樹は訊ねた。
え、とヒョットコみたいに洋一は唇を尖らせる。「電話がありましたので」
思いあたる節がないといった様子で二人は不思議そうに顔を見合わせた。洋一が成り行きを説明すると、ようやく合点し、「あの時は気が立っていたからな」と悪びれもなく笑い声を上げた。
「拝見するに復縁されたようですね」
「復縁って大袈裟ね。ほんのちょっと言い合いになっただけじゃない」彼女は抓んだ米粒を見せびらかすようにする。「ちょっとよ」
「坂本さん、お怪我は大丈夫でしたか」
「だからさっきのはナツにツボ押しをしてもらってだけだっての」
「それではなく。乱闘中に包丁と聞こえたので」
「乱闘って大袈裟だな。ほんの少しじゃれ合ってただけっての」彼は抓んだ豆粒を見せびらかすようにする。「少しだ」
部屋の片隅にはズタズタに切り裂かれたワンピースが転がっていた。
事の発端はこうだ。
本日二人はデートする予定であった。夏樹が購入したてのワンピースでめかしこんでいたにも関わらず、浩介はそれに気づかなかった。そればかりか「どう、似合ってる?」の問いかけに対して「可愛い」の一言もなかった。それがきっかけとなりほんのちょっとした言い合いとほんの少しのじゃれ合いが勃発した、そうな。
呆れてものが言えなかった。
「でもいいの。コウちゃんが新しいワンピースをプレゼントしてくれるって約束してくれたから」
「おいおい、そんなこと約束したか」
「言ったよ」彼女は満面の笑みで浩介の腕に絡みついた。
呆れたが、少し微笑ましくも思えた。
その日は自転車を押して徒歩で帰宅した。駐輪場に停め、鞄をつかむと振動が伝わってきた。洋一は街燈の薄明かりを頼りに携帯電話を探る。着信は母からだった。
「もしもし、どうしたの」
『仕事……どうかなって思って』ぽつり、ぽつりと母は言う。
「さっき終わったところ。まあ、少し慣れてきたかな」
『ご苦労様。いつもこんなに遅いの? 八時過ぎよ……体調は崩してない?』
「僕は大丈夫だよ、母さんは?」
母との会話はいつも他愛ないものだった。仕事、体調、食事について、アンケートの文言を読み上げているかの形式的なもの。それでも母の心遣いを有難く思いながら、ひとつひとつ丁寧に返事した。
『まだ家にも着いてないのよね。そろそろ切るわね』
「うん、心配してくれてありがとう」
電話を切りかけると、母は小さく声を洩らした。数秒間の静寂が流れ、『ところで……父さんから連絡くる?』と母は訊ねた。
「たまにね」
『元気そう?』
「相変わらずだよ」
『そう……あ、切るはずだったのにごめんなさいね』
いいよ、と軽くうつむき、電話を切った。
階段を上り、ノブに手をやると鍵は開いていた。九日間か、愛子にしてはよくやったと褒めるべきか。彼女は何においても続いた試がない。幼い頃、功夫道場だけは二年間通ったらしいがどこまで本当だか定かでなかった。ふと、昼時に愛子からメールがあったことを思い出した。今日予定があったのだろうかと考えてみるものの、思い当たることはない。どうせ買い物に付き合わせたあげく、荷物持ちでもさせるつもりだったのだろう。
とにかく、今日も疲れた。
洗面台で手洗いとうがいをし、鏡を見た。痩せこけた血色の悪い男が映っていた。その男は深く溜息を吐いた。目の前に植物があったとしたら、瞬時に枯れ果ててしまいそうな死の息だった。
リビングに入るや、焦げた臭いに鼻が曲がる。
「おかえんなさい」愛子はテレビを観ていた。煎餅をかじっては床にぽろぽろと屑を零す。
洋一は鼻を抓み、頬杖をついて寝そべる彼女をすり抜け、ガラス戸を開けた。
「なんだよ、この臭い」
振り向きもせず、彼女はチャンネルをころころと替える。コンロにフライパンがあり、そこに石炭のような物体があった。元凶を突きとめ、換気扇をまわす。テーブルにあるカップラーメンから察するに、珍しく料理してみたものの失敗に終わったのは明白だった。
「使ったら洗ってくれないと、こびりついてとれなくなるだ……」洋一の目が点になった。「ペラピットじゃないか!」
ペラピットフライパンは洋一が愛用しているものだった。光沢を帯びていた純白の表面が炭窯にでも突っ込んだように真っ黒になっている。無惨にも変わり果てたその姿に嘆き悲しみ、抱き寄せる。
どうして女なのにこんなこともできないのだ、と頭の天辺に向かって血が昇る。
「これ高かったんだ。いくらかわかるかい? わからないだろう。一万九千八百円! フライパンに一万九千八百円だぞ。そりゃあ僕も贅沢だと思ったさ、でもどうしても欲しかったんだよ。僕はこれを購入するために大学の頃から五百円玉貯金箱にコツコツコツコツコツコツと貯めていたんだぞ。知っていたかい? 知らなかったよね。それに、どうせキミは焦がすんだから違うフライパン使ってくれよ。なぜペラピットを選ぶんだ。そもそもこれは二年使っても焦げないことがウリなのに、どうして一晩で二十年も使い古したようになってしまうんだ。どんな使い方をしたらこうなるんだ。全く信じられない。今度焦がしたら承知しないからね!」
テレビの電源を落とした。「承知しないって、どう承知しないの?」愛子は蝋人形のように白く作り物じみた表情で言った。
「どうって……」
「わかった。今度焦がしたらあたし出て行く。そしたら満足なんでしょ」
「出て行くってどういう意味だよ。そんな話をしているわけじゃないだろう」
彼女は立ち上がり、洋一を見上げた。「今日は休みだったはずだよね?」
「メモに残しておいただろう。仕事になったんだ」
「約束したのに」ふっとマッチの火を吹き消すようなもの言いだった。「洋一は平気で破るんだ」
先週、愛子が休日を気にしていたのを思い出した。
「約束と言っても予定立てていなかったじゃないか」
「予定がなかったら破ってもいいわけ」
「じゃあなにか。急な仕事を交際相手との約束がありますからと断れば良かったのかい」
「断ればいいじゃない」彼女の口調が徐々に荒くなる。
「職務を全うすることがどうしていけないんだ。いいかい。仕事と恋愛は比べるものじゃないんだよ」
「比べてないわよ」
「じゃあ、なぜ怒鳴るんだ」
「もういい!」
叫ぶと同時に愛子の背後でガスバーナーを点火したような音がした。
放屁だ。
「こんな時に放屁をするんじゃない」洋一は溜息をつく。
「オナラくらい自由にしたっていいじゃない」
捨て猫に同情するような深く憐れんだ目つきに洋一はたじろいだ。彼女は瞼を閉じ、寝室へと消えた。
わだかまりを抱えたままフライパンをこする。さすがペラピットと言うべきか以前の艶をすぐに取り戻した。薬缶で湯を沸かす。とてもじゃないが料理をする気力はなかった。カップラーメンに熱湯を注いだところで、愛子が足早に現れテーブルに何かを置いた。
リボンのついた黒包みの小箱だった。
「今日、なんの日か憶えてる?」
言葉を詰まらせ、視線をカレンダーへと泳がせる。今日は十月二十八日。なんだ。十月二十八日、十月二十八日、頭の中で反芻する。
「あたしは洋一からプレゼントされたあの日のこと忘れてないのにな」
――付き合ってもないのに鍵なんか預かれるわけないでしょ。
リボンがほどけるように口が開いた。
「ようやく思い出した? 三年目の記念日だよ」能面のように無表情だった。
「……ごめん」洋一はそれ以外の言葉が思いつかなかった。
もう一度謝るが「もういいって」と一蹴される。
「それ、あたしからのプレゼントだから。どうせなんにも準備してないから言うけど、お返しとかいいからね」
「そういうわけにいかないだろう」
「どうして? 忘れてたんだから一緒じゃない。プレゼントなんて義務として贈るものじゃないでしょ」
言い返すこともできずただ黙り込んだ。何と言えば彼女の怒りがおさまるだろう、ただその一点に思考を収斂させる。愛子は頭を透かし見たように口元を緩めた。穏やかな笑みだった。
「安心して。怒ってないから。別に期待もしてなかったし。三年もすると怒ったり傷ついたりすることが減るから不思議よね。これから先、あたしたちどうなるんだろうね? なんだか……心がどこか遠くに行っちゃうみたい」
彼女は踵を返した。
幼少期、両親と神社の境内を歩いた記憶がある。ひどい人だかりで、周りにいる大人がいつもより大きく見えた。それでも不安感はなかった。逸れぬようにと父が手を繋いでいたから。その隣で母が見守っていたから。土みたいにざらついた父の手、海みたいに波うつ母のまなざし。どうしてかその思い出が不意に蘇り、心に溢れる。あの時は笑っていた、みんな。
「なによ」と愛子は言った。
無意識に彼女の肩をつかんでいた。
「僕が悪かった。話をしよう」
「なにを話すの? 洋一が記念日を忘れてたのは事実だし、あたしはそのことに対してどうしてほしいなんて思わないの」幼子を諭すようなゆっくりとした口調だった。
「ごめん。最近仕事が忙しかったんだ」
「ねえ聞いていいかな。怒らないでほしいんだけどさ。自分の恋愛も満足にできないのにこんな遅くまで一体なにをしてるの? 誰を支援してるの? あたしラブマネさんの仕事ってよくわからないけど、はっきり言って洋一は向いてないと思うの」
彼女の言葉は刃物となり洋一を切りつけ、途端脱力感に襲われた。
「疲れてんでしょ? 早く休んだ方がいいよ」自身が言うように怒りや悲しみはなく平生の彼女と全く変わらない調子で言った。「おやすみなさい」
寝室の戸が閉まり、しばらくしていつも通りいびきが聞こえてきた。プレゼントの包みを丁寧に開く。中には黒いリストバンドが入っていた。
元々他人とコミュニケーションをとるのが得意ではない。むしろ不得手だ。幼い頃から独りでいることが多かったし、休日も大抵は家で過ごす。宅配便の配達員と顔を合わすのさえ鬱陶しい時もある。
他人の恋愛に関与し、無茶な要求にも笑顔で対応しなければならない。そんな違う自分を演じるのが正直つらかった。百永美が頭を過る。ストレスにならない相手もいるがごく僅かだ。
愛子が言うようにきっとこの仕事は向いていないのだろう。なぜこの仕事に就こうと思ったのか。記憶を辿ろうとするものの、それは広大な砂浜に埋もれた何の変哲もないひとつの貝殻を掘り出すように、ひどく困難で、ひどく億劫に思えてならなかった。
なので、考えることをやめ、ラーメンを啜ることにした。
『おかえんなさい、ラブマネさん』その5へ続く
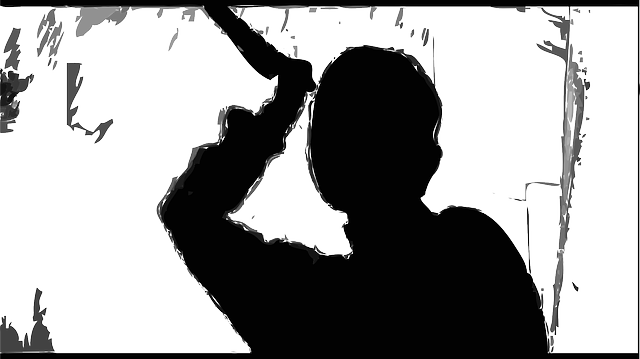
-640x360.jpg)




