こんにちは、宮比ひとしです。
この記事では、オリジナル小説である『おかえんなさい、ラブマネさん』その3を紹介します。
恋愛支援専門員(通称ラブマネージャー)である青年が、個性豊かな利用者の恋愛支援に奮闘するラブコメ小説となっています。


おかえんなさい、ラブマネさん その3
十月二十七日 木曜日
ダダダン! ダダダン! ダダ ダダ ダダ ダダン!
目を醒まし、眼鏡を嵌める。テーマ曲に合わせてボジラが喚いていた。背ビレを押すと、ぴたりと静まった。新品をしまっておくのももったいないからと、スピーカーにセロハンテープを貼ることで音量を抑え、洋一が使っていた。
トイレの便座に腰を下ろす。
トイレットペーパーが床についていない。
昨夜、最後に使用したのは愛子だったので、てっきり力尽きた一反もめんとばかりに垂れ下がっているかと思っていた。ようやく改心したか、とスッキリ用を足す。
紙を取ろうとして手が空振った。ペーパーホルダーを上げるとそこには芯しかなかった。彼女が使い切ったまま交換しなかったのだ。やれやれ、と下半身丸出しのまま棚に積んだロールを取り出した。
洗面台で顔を洗う。飛沫があらぬ方向に飛ばないよう、おしとやかに。
先週から水をあげているのでモンステラの葉は艶々としていた。テレビの電源をつけ、『ニッポンの朝』にチャンネルを合わせる。男性アナウンサーが落ち着き払った声で何やら報道していた。熱したフライパンに、さやいんげんとしめじを転がしながら耳を傾ける。
テーブルに二人分の朝食を並べているとテレビで恋愛保険との言葉が発せられた。牛乳を一口飲み、音量を上げる。内容は十年前に制定された恋愛保険法の見直しについてだった。
――なんだってこんな法律できたんだろ。
大学生の頃二人でテレビを観ていた時だった。ニュースで恋愛保険が取り上げられていたのを見て、愛子が口にした。
離婚率の増加、少子化、相次ぐドメスティック・バイオレンス、児童虐待を背景に恋愛保険法は制定された。厚生労働省の定める開設基準を満し、都道府県によって指定を受けた飲食店やレジャー施設、ラブホテルなどが恋愛サービス事業者と位置づけられ交際支援の受け皿を担うこととなった。そして、恋愛保険制度の導入に伴い、要となるべく創設された国家資格こそが恋愛支援専門員だった。
――制定されてから出生率も増えたし、離婚率も年々減少。統計からも明らかだよ。立派な成果だ。
――なんか恋愛保険って名称からして胡散臭いのよね。ぷんぷん臭うわ。それに納得いかないの。お互いが好きで付き合うのに他人の許可がいるなんてさ。
――許可なんていらないさ。交際を決めるのも当人の自由だしね。ただ、保険控除を受けるのに手続きが必要なだけだよ。
――同じことじゃない。見てみ、ニュース。七十のおじいちゃんが恋愛だのラブだの連呼するもんだから笑えてきちゃう。
当時の厚生労働大臣である焼野氏だった。ふさふさと蓄えた白い眉毛から魚のようにぎょろりとした目玉をちらつかせていた。
気づくと、ニュースは次の話題に移っていた。朝食を済ませ、弁当箱に白米、鮭の切り身、温野菜を詰め込んでいく。次にスポンジを泡立て、油汚れが残らぬよう何度も食器をこする。なぜかしら、先日フライパンがベトついた状態でしまってあったので、より念入りに洗うことにしていた。
着替えをし、カレンダーを見ると二十七には赤丸がついていた。愛子は休みだ。声をかけようか迷ったが「そろそろ行ってくるから」と肩を叩いた。
愛子はむくりと起き上がると「おはひょわわわう」と欠伸まじりで挨拶した。
「朝食は用意してあるから」
「はひはほう」
靴を履いていると、腋を掻きながらとぼとぼと彼女が歩み寄ってきた。
「ひってらっひゃい」
玄関扉を開くと、愛子に呼び止められた。
「今日帰り何時くらいになりそう?」
「わからないよ。何時だっていいじゃないか」
「よくないの。あたしにだって都合ってものがあるんだから」
どんな都合があるというのだ。休みの日は掃除も洗濯もせず、ぐだぐだと寝転んでいるのではないか。
「いつもと同じくらいだよ」そう言い残し、出発した。
「ラブプランって、ラブマネの性格でるよね」
百永美の恋愛支援計画を立てていると、一ノ瀬が横から太い首を突っ込んできた。恋愛支援計画とはラブプランの正式名称である。ラブマネージャーだとかラブプランだとか、この業界は赤面なしに口にするのが困難な用語が多い。が、恋愛支援専門員は一種の職業病のように恥ずかしげもなく言葉にする。
「覗かないでくださいよ。やりにくいです」
「いいじゃないの。わたしとヨウくんの仲だし、減るもんじゃないんだし。ほらほら」強引な托鉢僧みたいに彼女は両手を器にする。
「お断りします」
おしくらまんじゅうのように揉み合っていると、四谷所長がのっそりと顔を上げ視線を注いでいた。が、注意することなく、そのまま手元の書類へと視線を戻す。叱りたければ叱ればいいのに、だからナメられるのだ、と内心で悪たれた。
「先輩に見してみ。アドバイスを聞くことも大切よ」隙をつき、その豊満な身体で洋一を弾き飛ばす。「なになに。彼女の希望は『喧嘩なく穏やかな生活を送りたい』。短期目標は『彼の機嫌を損ねる発言は避け、月に一度は御馳走をもてなす』ですって」
「声に出して読まないでください」
「なによこれ。もてなすって。家政婦じゃないんだから。男尊女卑も甚だしいわね」膨れ面をさらに膨らまし、ふてぶてしく頬杖を突く。
「彼女にとってのプランですから、自己啓発ですよ。それに僕は担当したのが男性だとしても同じことを書きます」
「『サービスを利用しながら二人で楽しい時間を満喫する』でいいのに。ヨウくんは細かいって言うか融通が利かないって言うか。ミカちゃん、プラン見せたげなよ」
デスクに置かれたブックラックから厚化粧の銀髪女性が顔を出し、「私のプランが参考になるんスカね」と返事した。
誰だ! 洋一は思わず椅子から転げ落ちた。
「どうしたんスカ。影沼さん」銀髪女性はボールペンがのっかりそうなほどかさばった睫毛をぱちくりと上下させる。
「え、いや……六本木さん、ですか?」ずれた眼鏡を戻しながら立ち上がった。
まさしく六本木美加だ、間違いない。彼女に何が起こったのか、黒だった髪はパンクロッカー風の逆立つ銀色で、薄紅の頬はマントヒヒの尻みたいに真っ赤だ。以前の落ち着いたイメージの欠片もないほど変貌を遂げていた。
「ミカちゃんにも驚いたけど、今頃気づくヨウくんにもビックリだわ。ラブマネたるもの外見の変化に敏感じゃなきゃダメよ。そんなんじゃ利用者の大切なシグナルを見逃しちゃうわよ。まあ、それはいいとして、早くプラン見せてあげて」
一ノ瀬が催促すると、美加はデスクに重ねていたカルテの背表紙を指でなぞり、うーんと唸る。
「刺激的なの頼むわよ」
「結婚して二十年目の方なんスけど」彼女はカルテごと一ノ瀬に手渡した。
アセスメントを洋一は横から流し読みする。五十八歳の男性、社会人なりたての娘が一人、警察官、趣味は盆栽。さらに備考欄には厳格な性格とあったので洋一は担当している濱崎極の姿を自然と思い浮かべていた。彼は定年退職しているがそれ以外は一致する。
用紙を捲り、恋愛支援計画書を拝見する。短期目標は『サンタクロースに扮装をしてプレゼントを渡す』、長期目標は『妻をあだ名で呼ぶ』とあった。
「これは……シ、ゲ、キ、テ、キ!」一ノ瀬は興奮して両頬を押さえた。
洋一は唖然とした。本人の押印があることに何より驚いた。利用者の性格にもよるだろうが、この計画を五十代の男性に提案するのは勇気のいる所業である。
「よくこれをご本人様が了承しましたね」
「だって、いつまでもトキメキを持っててほしいじゃないスカ。最初はすごく怒鳴られたけどなんとか説得できたんス」
外見だけでなく内面も変わったようである。
「チャレンジャーだわ」一ノ瀬はカルテを返し「どう、参考になったでしょ」と言った。
「はい。いろんな意味で」
「ミカちゃん、前は奥手奥手だったのにね。最近彼氏ができたせいね」
「いやスね、彼氏なんて」マントヒヒの尻をさらに赤くした。
彼女の激変に合点がいった。
「まだ友達ス」
交際せずにこの変化。交際するとどうなってしまうのか。
「ヨウくんもミカちゃんにプラン立ててもらったらどう」
「結構です」洋一はきっぱりと断った。
「影沼さんって、自己作成スカ?」美加が訊ねた。
はい、と頷いた。
計画書は必ずしも恋愛支援専門員が作成せねばいけないわけではない。自身で作成しても市役所の許可がおりれば問題はない。
「なんなら、わたしが作ってあげてもいいけど」一ノ瀬が仕方なさそうに言う。
「なお結構です」
「でもさ彼女さんと同棲してるんでしょ? そんなプラン立ててるようじゃ、そのうちに愛想つかされちゃうわよ」
一ノ瀬に茶化され、どうしてか胸がざわついた。首を振る。あれだけ自由奔放に振る舞う彼女が何故に愛想をつかす理由があろう。こちらには多分にあるがね。
買い物袋を片手に愛子はオレンジロードを歩いていた。オレンジの樹木に添って、スーパーマーケットに服屋、電気屋と様々な店舗が並ぶ、通称オレンジロード。木洩れ陽が地面を踊り、愛子はスキップするように陽のあたる部分を踏みしめ、ジグザグに進んでいく。通行人や自転車も何のその、かろやかに次々とかわしていく。木洩れ陽が途絶えた所で顔を上げると、そこは見慣れぬ景色だった。辺りを見まわすが全く見当がつかない。直進していたとばかり思っていたのに知らず知らず逸れてしまったようだ。
「また迷っちゃった」唇を突き出し、右手首のリストバンドを見つめた。
何の前ぶれもなく突風が吹いた。舞い上がるスカートを押さえる女性に、数人の男がとっさに反射する。ハーフパンツにスニーカー姿の愛子には誰一人見向きしない。すると、円盤形のUFOが着陸するように麦わら帽子が足元に飛んできた。拾い上げると前方からリュックを背負った男が小走りで近寄ってくる。
「す、す、すみません。ぼ、帽子が飛ばされちゃって」ぽっちゃりとした頬に汗が流れる。
どうぞと差し出すと、男は何度も頭を下げ麦わら帽子をかぶった。おにぎりも一緒に渡したくなるような風貌だった。
「じゃ、じゃあ、失礼します」
「すいません。あたし迷っちゃって。ここはどこですか」
「ど、どこって言われても」男の黒目がオタマジャクシのようにチョロチョロと泳ぐ。「ど、どこへ行かれるんですか?」
いつも目印にしている喫茶店『ドッグ』の名を出すと男は頷いた。
「そ、それなら。この道を真っ直ぐに行った下着専門店『ブリーフ&トランクス』の前にあるミラーを右に曲がって、四十五歩ほど歩いた先の石焼イモの屋台と定食屋『ねこまんま』の間の通りから三番目の交差点の左斜め向かいにあります」
愛子は首を傾げた。「もう一回お願い」
「この道を真っ直ぐに行った下着専門店『ブリーフ&トランクス』の前にあるミラーを右に曲がって、四十五歩ほど歩いた先の石焼イモの屋台と定食屋『ねこまんま』の間の通りから三番目の交差点の左斜め向かいにあります」男はもう一回説明する。
愛子は両手を合わせ懇願する。「もう一回!」
男はもう一回説明するが、やっぱりわからなかった。
「こ、こ、この道を真っ直ぐに……」
「ちょちょちょちょと待って、ちょっと待ってよお兄さーん。もう埒が明かないから案内して」
男は戸惑うものの快く店先まで案内してくれた。
ありがとうございます、とお辞儀すると満足そうに男は去っていった。
喫茶店の脇道に入ると閑静な住宅街が建ち並んでいた。しばらく進むとレゴブロックみたいに角ばった白い建物が見えてきた。塀に埋め込まれた表札の横にあるインターホンを押す。ほどなくしてドアが開いた。
「さ、入れよ。愛子」
新田貴彦は買い物袋を受け取り、愛子の住むアパートの数倍はある広々としたリビングへと招き入れる。
「ご苦労さん」貴彦はそう言って水を寄こした。
喉を潤す。かすかにレモン味がした。彼は相変わらず日焼けサロンに通い詰めているかのようなミルクチョコレート色の肌に、袖捲りした腕は無駄なくひきしまっている。ふと、掛け時計を見て約束の時間より十分遅刻していることに気がついた。
「あっ、遅れてごめん」
彼は時計を見上げた。「本当だ。でもさ、そんなこと謝るなよ。俺が気にするわけないだろ」
「気にする人もいるのよ」
ぶつぶつと文句をたれる洋一の顔が浮かぶ。
「それより、ここのところしょっちゅう来てるけど洋一くん……だっけ? 彼にばれてないの?」
「ダイジョブ、ダイジョブー。変なトコ細かいくせに割と鈍感だから」
棚にはたくさんの写真が飾ってあった。主に貴彦と妻である伸枝が写っている。結婚式、新婚旅行、その中には野球のユニフォーム姿の彼の写真が数枚交じっていた。中学に入学したての彼の腕には深紫色のリストバンドがある。
愛子は右腕を見た。この頃はまだ貴彦がしてたんだった。
「なに見てんだ」
愛子は高校時代の集合写真を手に取り、意地悪く言った。「伸枝先輩とはこの頃から付き合ってたんだね。あたしに黙って」
彼は何も答えない。
「諏実高校野球部、甲子園予選の準決勝……敗退か。懐かしいね」
四番打者の貴彦、マネージャーを務めていた愛子と肩を組んでいた。その陰に隠れるようにして伸枝がいた。彼女もまたマネージャーだった。
「貴彦と伸枝先輩が結婚したなんて今でも不思議」
「なんだ、寂しそうだな」
「馬鹿言わないで。あたしは祝福してるの」
伸枝が由緒正しい家柄だったため婚約に至るまで随分と苦労していたのを知っていた。反対され駆け落ち寸前だったが、あることを条件にようやく了承を得ることができた。だから、自分だけは二人が結ばれたことを心から祝福しようと決心した。
「うまくいってるの?」写真を戻し、訊ねた。
「まあ、いろいろあるさ」
彼の片眉がぴくりと跳ねる。触れられたくない話題になった時の癖だとわかっていたが愛子は続けた。
「しっかりしてよ。まさか、あたしのせいで喧嘩になったりしてないでしょうね。迷惑だったら言ってよね、もう止めるから」
「喧嘩になんてなってないさ。愛子が来てるの伸枝知らないしな」
「なんでよ。ちゃんと言っといてくれなきゃ」
「俺と愛子の仲じゃないか。わざわざ言う必要もないだろ」
「なに言ってんのよ、ダメに決まってるじゃない。伸枝先輩が居ない時におじゃましてるのも気が引けるのに。あたしが先輩と気まずくなるんだから」
「平気だって。それに伸枝とは別居中なんだ」
「ええ! やっぱり喧嘩してるじゃない」愛子は責めるような口調で言う。
「違うって。口論なんてここ数年してないしな。嫌なことがあれば冷静に話し合うし」
「そしたらなんで別居になるわけ」
「例の出演がバレてな」
あーあ、と愛子は嘆く。「だから、やめとけって言ったのに。ああいうの伸枝先輩が苦手なのわかってたでしょ」
「いい稼ぎになるんだよ。伸枝には不自由ない生活をさせてあげたいんだ」
「それがきっかけで喧嘩になったのね」
「だから喧嘩じゃない。実家で考え直したいって言うから俺も納得した。お互い冷静だった」彼はあっけらかんとしていた。
「もう。喧嘩した方がマシなくらいじゃない」
「そうそう愛子も出演してみないか?」
「やあよ。そんな恥晒しみたいなことできるわけないでしょ」
「本気でやっている子に失礼じゃないか。女優目指してるのもいるんだぞ。それにイメージビデオみたいなものだよ。恥ずかしいことはない」
「あたしはいい」
きっぱり断ると、本気で勧誘するつもりはないらしく、貴彦は買い物袋からタマネギとひき肉を取り出していた。
「今日もごちそうが楽しみだ」
「思ってもないこと言わないでよ」
「そんなことないさ。愛子が努力して作ったんだもの。俺にとって、この上ないごちそうだよ」
「あたし、やっぱ料理苦手なんだよね」
うつむく愛子の髪をくしゃくしゃっと撫でた。「気にすんなって」
いつも勇気づけられてきた言葉。
愛子は腕捲りして肩を鳴らす。「よっしゃやるか」
「そのリストバンドまだつけてるんだ」彼は白い歯を零して笑った。
「あたしの勝手でしょ。貴彦に迷惑かけてるんじゃないんだから」
「お先に失礼しまス」
そう告げると美加は化粧を厚く塗り直し退出する。薄闇に銀のトゲトゲ頭が吸い込まれていった。今夜も社内に残っているのは四谷所長と洋一だけだ。女性二人がいなくなると途端に静けさが増す。キーボードを打つ音だけが響いていた。
時計の針はすでに七時半をまわっていた。数時間、白光する画面を凝視していたので瞼が重い。尻も腰も肩も痛い。眼鏡のレンズ裏に指先を入れ、瞼をこする。風船が萎むように急速に集中力が失われていくのを感じつつも、本日中に仕上げねばならぬ書類をどうにか終え、パソコンの電源を落とした。
ようやく帰れる、そう思ったところ電話機が鳴った。
こんな時間に誰だ。電話機はデスクごとにある。出てくれないだろうか、と四谷所長に目配せするがナマケモノさながらピクリとも動こうとしない。洋一は聞こえないよう小さく舌打ちをし、受話器を取った。
「美鷹恋愛支援センター影沼です」
ごほほんと咳があった。こんばんは、と重々しい男の声が続く。即座にその声の主が濱崎極であることを察した。と、同時に嫌な予感がした。
『影沼くんだね』
「あっはい。そうです。どうなさいましたか、こんな夜分に」
『どうしたか、じゃないよ影沼くん。保険どうなってるのかね』
徐々にボリュームを上げる濱崎の声に自然と身体が委縮する。
「保険、ですか……」
パソコンを切ってしまったことに後悔しながら棚からカルテを取り出す。
『今日、仕事帰りに旅行会社に寄ったんだがね。そしたらどうだ、保険の期限が切れていると言われるじゃないか。これは一体どういうことなのか説明してもらえんかね』
まさか、そんなはずはない。カルテに挟み込んである恋愛保険証の写しを確認し、頭が真っ白になる。保険の有効期限が先月で切れていた。慌てて手帳を開く。保険の更新者は毎月チェックしてあるのだが記されてない。完全に抜け落ちていたのだ。本来であれば、先々月に申請をし、先月には認定がおりていなければならない。
「申し訳ございません。手違いがありまして」
『手違い? なんの手違いだね。単に忘れていただけじゃないのかね』
言葉が詰まった。正直に「はい、忘れていました」と答える。
『忘れていたじゃ困るんだよ! 影沼くんの失態で今日旅行の予約がとれなかったんだよ。どうしてくれるんだね』
電話機に何度も謝罪する洋一を見て、四谷所長はかすかに唇を緩めていた。洋一は屈辱感から下唇を噛みしめる。
『謝ってもらっても仕方ないんだよ。どうなるのかね。認定がおりるまで私は旅行に行くこともできんのかね』
「そんなことはございません。暫定利用ができます」
『ざんてい?』
先日、百永美に説明した内容を繰り返した。通常は申請、調査、審査会の段取りには約ひと月かかる。その間、おりることを見越してサービスを利用する。一旦全額支払うことになるが、認定決定後、支援度に応じた一部負担を差し引き返還される。
『戻ってくるのは確かなんだろうね』
「おそらく支援二は間違いないかと思います」
『そうかね』と声が和らぐのも束の間、『影沼くん、一旦全額支払わねばならないのは変わりないんだからね。遊びでやってもらっちゃ困るんだよ。とにかく手続きを頼みたいんだがね。印鑑が必要なんだろう。早急に来てくれるかね』と言い放つ。
手帳を見ると明日は休日となっていた。「では、明後日の土曜日でしたらおうかがいできますがご都合いかがでしょうか?」
『私はね、早急にと言ってるんだよ。聞こえなかったのかね、影沼くん!」話の通じない奴だと言わんばかりに口調を荒げる。「土曜日は市役所が休みじゃないか。今日はもう遅いから明日中に頼むよ。いいね」
いいね、も何も断りでもしたら、どれほど叱咤されるかわかったものじゃない。仕方なく明日の訪問を約束する。
『退職したといっても嘱託でなにかと忙しいんだ。ラブマネだかなんだか知らんけどね、保険の手続きをするだけの仕事とは違うんだよ。ぎっしりと予定が詰まっている。その中でわざわざ影沼くんとの時間を割くんだよ。担当者ならそういうことをわかっててもらわないと迷惑するのはこちらなんだからね」
威圧的な咳払いを残し、通話は切れた。洋一は深い溜息を吐きながら受話器を置く。四谷所長のしょぼくれた目がこちらに向いていた。
「所長、明日出勤しますから」
四谷所長は興味なさそうに、そうかねと頷くだけだった。
アパートに到着すると洋一はインターホンを押した。しばらく待ってみるが音沙汰がない。もう一度、インターホンを鳴らし腕時計の秒針を見つめた。
一分が経過した。
魚眼レンズから覗き込むが室内は真っ暗だった。
「なんだ。もう寝てるのか」
二重ロックしていないことを祈りつつ鍵をまわす。幸い、U字ロックは掛かっていなかった。リビングの電灯をつける。寝室の襖は閉まっていた。いやに静かだ、いびきが聞こえない。寝室に愛子の姿はなかった。部屋中探してみるが案の定どこにもいなかった。
時刻はもうすぐ九時だ。こんな時間までどこをほっつき歩いているのだ。テーブルに目をやると、ぽつねんとメモがあった。
『今日おそくなる。レーゾーコにごはん入ってるよ』
相変わらずハンマーでかち割られたかのような珍妙な文字だった。が、その文字がふと愛らしく思えた。わくわくし、冷蔵庫に手をかけていた。
ぴたりと動きを止めた。
いや落ち着け。冷蔵庫だからって期待してはいけない。
ゆっくりと開けつつ、自身に言い聞かせる。
そうだ! きっとコンビニ弁当だ。そうに違いない。それ以上は期待するんじゃない。いいな、わかったね? オーケー。よし!
中にはご飯があった。
両手で握ると、わなわなと身体が震えた。
「どうして、どうして……どうしてパックのご飯を冷蔵庫に入れてるんだよ!」
それはレンジで温めるタイプのご飯だった。ガックリとうなだれた。そのままスライムのようにべったりとフローリングにへばりついた。濱崎の一件があったせいで、今日はひどく気が滅入った。もうこのまま眠ってしまいたかった。
目を開く。眼鏡をくいっと上げ、身体に鞭を振るい立ち上がった。有り合わせの食材でおかずを作り、夕食を済ますとシャワーを浴びた。パジャマに着替え、歯磨きをした。布団を敷き、ボジラの目覚まし時計をセットする。十二時を過ぎていた。
愛子はまだ帰ってこない。
『おかえんなさい、ラブマネさん』その4へ続く


-640x360.jpg)
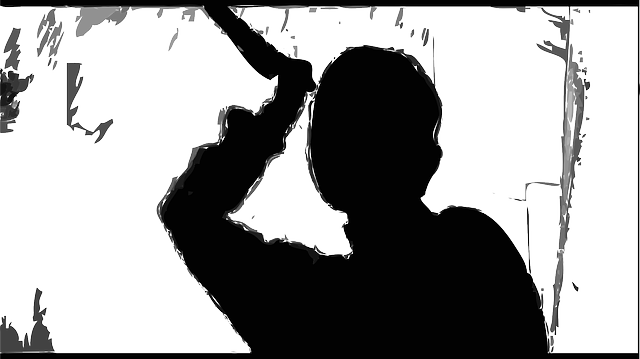
-640x360.jpg)

