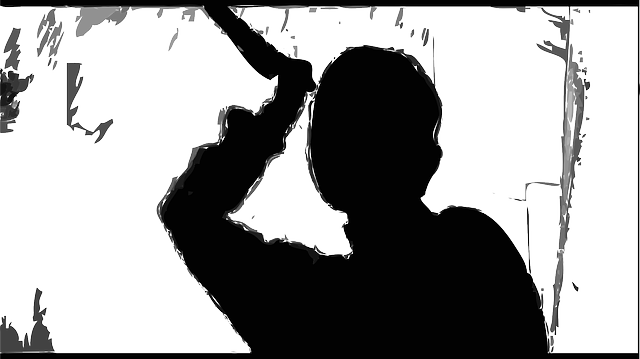こんにちは、宮比ひとしです。
オリジナル小説『母とのシエスタ』その3です。
ポカンとなったアンポンタン・ポカン
「どうやって行くんだい? 僕は車の運転はできないよ。ビール呑んじゃったからね」玄関框でスニーカーを履きながら僕は言った。
「かあさんもできないわ。二十年ペーパードライバーなの」
「知ってるよ」
「それにしてもペー、パーって不思議な響きね」母は発声練習するかのように「ぺー」「パー」と何度か繰り返す。「かあさん何もできないドライバーみたいね」
「実際に運転できないしね」
母は玄関扉のノブを力強く回し、「まあいいわ。今日は自転車で行きましょう」と息巻いた。ガレージから普段買い物に使っているママチャリを出す。「あなたが漕いで。荷台にかあさんは乗って行くわ」
「二人乗りも飲酒も立派な犯罪だよ」
「犯罪に立派もヘタレもないの。多少のやんちゃをすることで、あなたは真のティーンエイジャーになるの。『ラブ・ユー・フォーエヴァー』に、そうあったわ」
「僕はもう二十六歳だよ」
「だから言ってるのよ」母はサドルをぽんぽんと叩いた。
「歩いて行く、という選択肢はないのかい」
「歩いて行けるところに枕屋さんはないわ。この近辺にあるのはコンビニ紛いの本屋さん、もしくは本屋紛いのコンビニだけね」
「辞典でも枕にすればいい」
「なにそれ。面白くない冗談ね。あなたお父さんに似てきたわね」
「親子は似るんだよ」
「血も繋がってないのに?」
「全く面白くない冗談だ」僕は諦めてサドルに跨った。
母を乗せて自転車を辷らせる。母は後ろできょろきょろと枕屋を探した。一時間ほど経ち、発見できぬまま隣町まで来てしまった。「枕屋、枕屋」と親と逸れた子どものように母は不安げな声を漏らしている。僕もなんだか不安になってきた。
「枕屋なんてこの辺にあるのかい」
僕はそもそも枕の専門店など聞いたことがなかった。
「枕は枕屋でしょ」母は悠然と言い張った。
ちょうど全国展開している蒲団屋を見かけたので「あそこはどう」と僕は指さした。
「あれはフトンって読むのよ」
「あそこなら、そこそこの品数が揃ってると思うんだ」
「それは枕の?」
「そうだよ」
僕がそう言うと、母は半信半疑で「じゃあ、騙されたと思って覗いてみましょうか」と言った。
駐輪場に自転車を停め、建物に向かった。自動ドアは僕達を招き入れるように素早く開いた。店内の案内に従い、枕のコーナーへと歩を進めた。枕ゾーンへ足を踏み込むと、さっそく女性店員が「どんな枕をお探しでしょうか」と営業スマイルで現れた。
「眠れないの」母は言った。
店員は鷹揚と顎を引き、さも睡眠不足が祟って衰弱した息子を看取るように悲痛な表情を浮かべる。店員は胡麻擦りをしながら様々な枕を勧めた。一つ一つの肌触りや入眠効果を熱心に説明し、その間もずっと胡麻を擦っていた。
「なんで胡麻を擦っているんですか?」僕はとうとう聞いた。
比喩ではなく店員は擂粉木と胡麻の入った擂鉢を抱えている。まるで探偵に証拠を突きつけられた真犯人のように訥々と語り出した。「胡麻の香りにはリラックス効果があるんです。枕にそれを含ませた……まだ売場に出ていない新製品なんです」
母の眼が獲物を捉えた鷹みたいにぎらついた。眉間に皺を寄せ、阿吽の像の如くに胸を張った。ゆっくりと口を開く。
それを見せて!
とは、言わなかった。「ふうん」と鼻息を漏らし、塵が眼に入っていたのかごしごしと袖でこすった。意気消沈とする店員がなんだか気の毒に思えた。
「羊がいいわ」母は急に言った。
店員は背後から槍で突かれたように「え、羊ですか」と慌てふためいた。
「そう。毛で覆われたあの羊よ」
「調べて参りますので少々お待ちください」
店員は踵を返し、足早に奥へと姿を消した。
「どうして羊なんだい」
「眠れない時に羊が一匹、羊が二匹って数えるじゃない。羊の枕ならきっと安眠できると思うの」
「それなら鼠にするべきじゃないかな」
「鼠? なんでよ」
「もともと、眠りsleepが変化して羊sheepになったんだ。眠ると羊を数えるなんて、マイクテストで〈本日は晴天なり〉と言うようなもんだよ。It's fine todayの発音には音声周波数が満遍なく含まれているから意味があるのであって、日本語では無意味なんだ」
「だから、なんで鼠なの」
「ネムリとネズミ。似てるだろう。それに日本人には鼠の方が馴染み深いんだ。昔話にもよく出て来るしね」
「鼠は嫌いなの。枕元にいると思うとぞっとするわ。でも、羊を数えると眠れるの。かあさん試したことがあるの。今日は駄目だったけど、何度か成功したこともあったわ」
「それはカズを数えること自体が効果的なんだよ。羊のおかげじゃない。『ドン・キホーテ』では山羊を数えていたしね。要は単純作業が入眠を誘うわけだよ」
「ドン・キホーテだか、ボン・ボヤージュだか知らないけどね、母さんは羊がいいの。絶対にね」
擂鉢に代わり枕を抱え、店員が戻って来た。けれども、心なしか暗鬱としている。案の定「羊はありませんでした」と頭を垂らした。
「そんな!」と母は絶句した。「そんな……せっかく羊なら眠れると期待してたのに。どうにかならないんですか」
「こればかりはどうにもなりません」店員は口惜しそうに唇を捻じ曲げた。
母はその場で座り込み、店員の足元に縋りついた。
「でも……」そう言って店員は持って来た枕を差し出した。
土砂崩れによって出口が塞がった洞窟を彷徨う。暗闇の中でひとすじの光を発見した。それは数年ぶりの陽射だ。脱出できるかもしれない、そんな願いを込めて母は店員を見あげた。
店員が枕をひるがえすと、白い綿毛に覆われた生き物がデザインされていた。しかしながら、羊に比べると圧倒的に首が長かった。
「羊はありませんでした。しかし、アルパカならありました」
母の瞳が揺らいだ。苦しみから解放されたように頬が緩む。「構いません。羊もアルパカも似たようなものです」
店員が不敵に微笑んだ。
「かあさん、本当にいいのかい? 羊とアルパカは違うよ。羊はウシ科、アルパカはラクダ科だ。首だって長い。それに、ほら、声に出して数えてみるんだ。アルパカが一匹、アルパカが二匹ってね。きっと舌を咬んで悶絶してしまうよ」
母の唇がそっと開いた。
「アルパカが一匹、アルパカが二匹、アルパカが三匹、アルパカが四匹、アルパカが五匹、アルパカが六匹、アルパカが七匹、アルパカが八匹、アルパカが九匹、アルパカが十匹」
言い切った。澱みなく、まるでナイル川の流れのように。
「いいの。羊を断念してアルパカにほいほいと乗り換えるかあさんを見て幻滅したでしょう。でもね……かあさんはこんな弱い人間なの。許してちょうだい」
「本当にいいのかい」僕はもう一度訊ねた。
「もう決めたの」
僕にはもう何も言うことができなかった。酔ってるせいか、酔いが醒めてきたせいか、もの哀しくなった。
「では、お会計にご案内します」店員が掌でレジカウンターを示した。
「決めただけよ。買うとは言ってないわ」母はきっぱりと断った。
僕は唖然とした。
店員はポカンとした。
「何を言ってるんだい、かあさん。買わないでどうするのさ」
「買わないわ」
店員は母の言葉を察して、「まだご覧になられるのですね。失礼しました」と一歩下がった。
その瞬間、母は腋に枕を挟み、「ボン・ボヤージュ!」と駆け出した。
店員は先ほどのポカンに輪をかけたようにポカンとした。そのポカンとした表情に『ドグラ・マグラ』がふと頭の中を過った。店員は僕を見て、説明を乞(こ)うかのようにしたりと笑った。
僕は、僕に聞かれてもわからないよといった具合に首を竦め、母の後を追った。
母は自転車の荷台に跨り待機していた。警備員が血相を変えて追いかけてきたので、僕は必死にペダルを漕いだ。
「なんで盗んだんだい」僕は息を切らせながら訊ねた。
「言ってるでしょ。かあさんに欠けているのは適度な運動で、あなたに欠けているのは荒れたティーンエイジだってね」
その4「レジデンツ城の武器博物館」へ続く