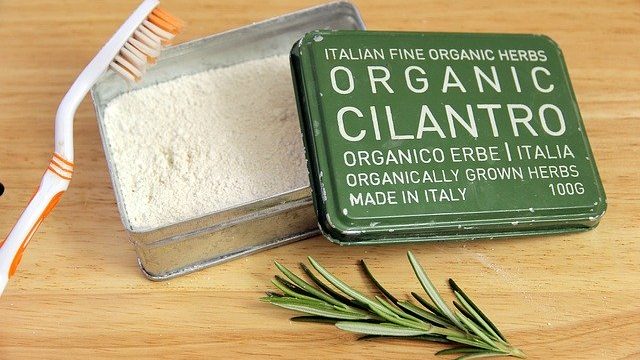こんにちは、宮比ひとしです。
オリジナル小説『母とのシエスタ』その4です。
レジデンツ城の武器博物館
結局、母は眠れなかった。
我が家に到着すると、眼の前では道路工事をしていた。リビングに入ろうが、扉を閉めようが、ドリルでコンクリートを掘り壊す音と地響きを和らぐことはできなかった。
母はローソファーに横たわり、アルパカの枕を敷き、羊を数えた。羊が千二十三匹通り過ぎたところで、アルパカが出現した。アルパカは五百ぴったりだった。次は鼠だった。七百八十二匹の鼠が過ると、突如に羊とアルパカが乱入した。入り乱れつつも行進は続いた。しばらくして母は数えるのをやめ、むっくりと起きあがった。総勢千六百八匹の大行進だった。
「この枕、ちょっぴりふかふかしてるの。かあさん、埋もれてしまいそうだわ。これじゃあ、眠れたとしても安眠するどころか息苦しくてうなされそう」母は窓に向けて鼻を鳴らした。「それにあの工事、うるさいったらないわね」
僕はグラスに注いだオールドパーを舐めながら「そうだね」と言った。首相にでもなった気分で国の行く末を憂慮しながら、ウイスキー独特の甘みを舌に絡ませる。
「あなた、工事をやめるように言ってきてくれないかしら」
「いくらなんでも無茶だよ」
「諦めてばかりいちゃ駄目よ」
僕は無言でオールドパーをぺろぺろと舐めた。
「かあさんに残された時間はもう僅かなの。時計を見なさいよ」時計の針は四時を回っていた。「こんな時間じゃ、とても昼寝なんて言えやしない」
「今日はもう諦めたらどうだい」
「あなたいつからそんなに意地悪な子になってしまったの?」
いつからだろうか。気づけば今の自分がいた。
いつから酒を呑み始めたのだろう。気がつけば昼間から呑んでいた。
母の言うことを素直に聞けなくなったのは、いつだったろう。
「あの……やめてもらえませんか」
僕は工事員に要求していた。
僕よりも幾分か若そうな工事員は眉を顰めた。「あん! なんだって?」ドリルを器用に扱いながら耳を傾ける。といっても、耳自体は安全第一とかかれたヘルメットにすっぽりと覆い隠されていた。
「やめてください」僕は怒鳴った。
僕の怒鳴り声はドリルの轟音によって掻き消された。仕方なさそうに工事員は中断する。ドリル音がやむと、耳がわんわんと悲鳴をあげているのに気がついた。我慢しながら「かあさんが眠れないからやめてください」と言った。
「そう言われても困るなあ」工事員は首から垂れ下げたタオルで汗を拭った。
「騒音で昼寝ができないんです」
「わかったよ。相談してくる」
意外にも工事員はものわかりがよく、髭面の現場監督らしき巨漢の元へと駆け寄って行った。僕は希望を抱いた。しっかりと想いを伝えることで世界から紛争がなくなるのでは、と思った。巨漢が顎髭を撫でつつ、こちらに歩んでくる。
「申し訳ないな、坊や。工事をやめるわけにはいかないんだ」
僕の希望は打ち砕かれた。
「どうしてですか」
「どうして? これが我々の仕事だからさ。我々は地面を掘り、舗装する。たとえ必要がなかったとしてもやらねばならないんだよ」
僕は言葉が詰まる。
「さあ、危ないから下がっていなさい」巨漢は言った。
「それは国土交通省の予算消化のためですか」
監督の胸板が大きく膨らんだ。そして、声をあげて笑った。
「坊や。仕事ってのはそんな簡単に割り切れるもんじゃあないんだ。我々は工事員だ。眼の前には道路がある。手にはドリルとセメントがある。これはもうやるしかないじゃないかね。そう思わないか」
「わかりません」
僕は仕事をしたことがないから正直わからなかった。
「しかし、これが答えなんだよ」
「でも、わざわざここじゃなくてもいいと思います。他に剥落したところがあるじゃないですか。ここは去年工事したばかりです」
「親方はそんなこと充分承知なんだよ!」若手の工事員はヘルメットをかなぐり捨て、憤慨した。
「じゃあ、なんで」
「坊や。道路が剥落していようが、いまいが、我々にとっては些細なことなんだ。庭に生えた雑草の長さが五センチなのか十センチなのか、それくらいに些細なことなんだ。本当に大切なのは掘ってみて、舗装してみて初めてわかる。汗水垂らし掘り起し、丹念にセメントで塗り固め、やれやれと一服して、初めて意味がわかるんだ」親方は諭すように言うと、僕の肩に手をのせた。「やらないうちは何もわからない」
若手の工事員は恋する乙女のように瞳を潤ませていた。
我が家に戻ると工事は再開した。
僕を見て、母は「あなたはいくつになっても頼りないんだから」と呆れた口調で言った。ドリルの地鳴りがいっそう激しくなった。まるで部屋ごとシェイカーに放り込まれ、カクテルでも作るようにシェイクされた。
僕は変わったのだろうか、変わらないのだろうか、一体どっちなんだろうと思った。
「もう一度、トライするの。あなたはやればできる子なのよ」母はそう言って鍵を手渡した。
「これは何の鍵なんだい」
「ガレージの奥にロッカーがあるの。その中から好きなのを持って行くといいわ」
憶えがなかったが、ガレージに向かってみると、隅っこに古ぼけたロッカーが闇に溶け込むようにひっそりと身を潜めていた。僕は鍵を差し込み、ゆっくりと回す。扉を開くと、僕はいつの間にレジデンツ城へと迷い込んだのかと思った。そこには武器博物館さながら様々な刃物が立て掛けてあった。ナイフ、斧といった刃物だけでなく、ハンマー、それに手榴弾まである。思いつく限りの武器と呼べる物がそこにはあった。
僕は悩んだ。どれを手にするべきか、と。
拳銃は物騒だし、ハンマーなんて僕の身の丈ほどもある。振り下ろしたら頭部が西瓜のように容易く粉砕してしまうだろう。そもそも、僕には持ち上げることができそうにない。熟考した末、僕はスタンガンを選んだ。これらの中では幾分か紳士的な雰囲気を醸し出しているように思えたからだ。
僕は意を決し、工事現場へと歩を進めた。すたすたと若手の工事員を過り、親方の前に立ちはだかった。
「ドリルをとめるように指示するんだ……さもないと」
僕は親方の鼻先でスタンガンの火花を散らせた。
「困るなあ」
親方は怯むことなく、むしろ差入の煎餅を頂戴するかのように、ひょいと取り上げた。
「いくらうるさいからって。これじゃあ、コンクリートは砕けないんだ。せめて、ハンマーでもあればなあ」親方は眉根を歪めた。
「それならありますよ」
僕は親方をガレージへと招き入れる。おまけに若手の工事員もひょこひょことついてきた。親方は軽々とハンマーを持ち上げ、寿司職人が出刃包丁を品定めするように、まじまじと眼を凝らした。
「うむ。これなら申し分ない」親方は唸った。
若手の工事員はプロパンバーナーを眼にし、ガラス越しにギブソンのエレキギターへ憧れを寄せる軽音学生のようにうっとりとしていた。
その5「チャーリー・ブラウン的、失われる『安心』」へ続く