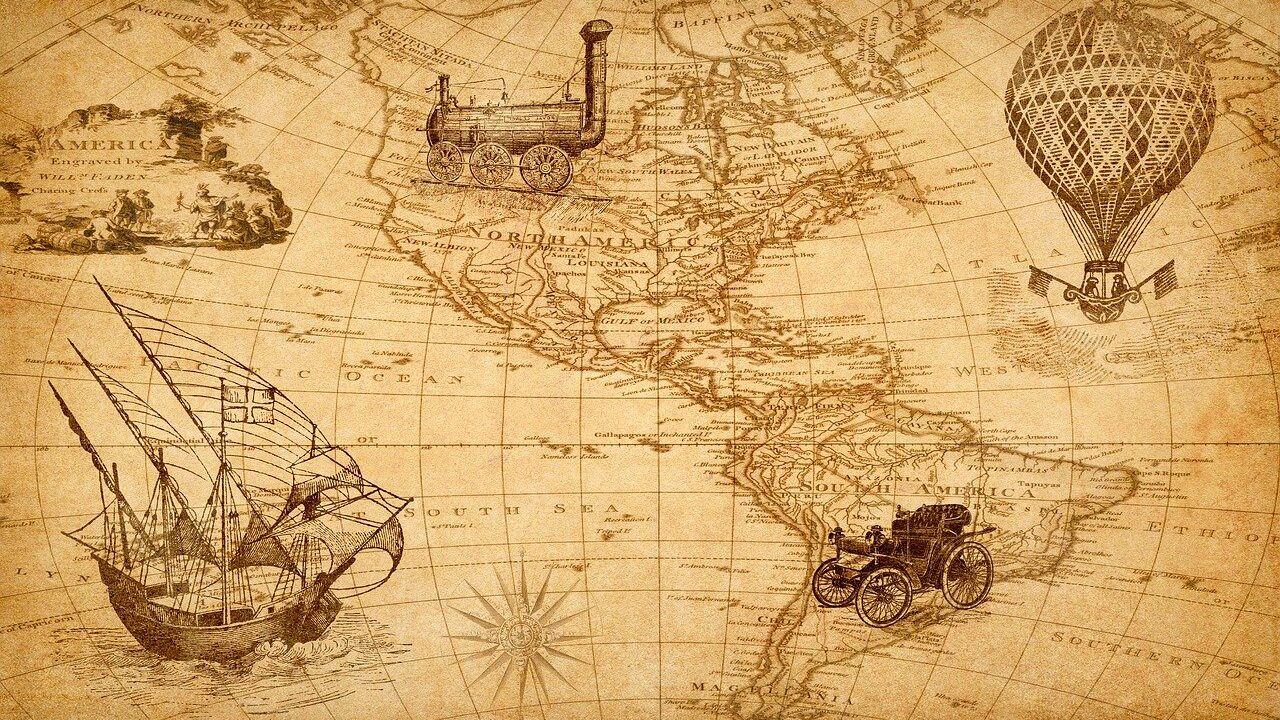こんにちは、宮比ひとしです。
オリジナル小説『母とのシエスタ』その2です。
天変地異、新大陸の形成、そしてメルティング・ポット
午後の一時半きっかりに、母は僕の部屋の扉を開いた。ノックの音とほぼ同時だった。
「眠れないのよ」母は言った。
「そうなんだ」僕は言った。
「眠れないの」母はもう一度言った。
腕に枕を挟み、夜遊びを覚えたての十代の若者のように母の瞳は爛々と輝いている。
僕はベッドに寝転んだまま「そうなんだ」と、もう一度だけ言ってみた。やはり、「かあさん、眠れないのよ」と母は訴えた。
僕はたった今まで読んでいたウラジーミル・ナボコフの『ロリータ』を伏せ、身体を起こした。「今朝、遅くまで寝てたんだよね。自業自得だよ」
自業自得という言葉にショックを受けた様子で母は俯いた。「たまに寝過ごすことが、そんなにいけないことかしら」
「そんなことないよ。僕なんていつもは十一時くらいさ。今日はたまたま九時に起きたけどね」
「どうして早く起きたの?」
「どうしてだろう。かあさんが寝坊していたおかげで洗濯機を回す音が聞こえなかったせいかな。音がしないから眼が醒めてしまった。静けさが僕を呼び起こしたんだね、きっと」
ふうん、と母は納得した。
「どうすれば昼寝できるかしら」
僕は悩んだ素振りをした。首を傾げ、拳を顎に引っつけ、さらに首を傾けた。
「今日は昼寝するのをやめたらどうだい」
「駄目よ! 昼寝しないと身体のリズムが狂っちゃうの。今寝ないときっと夕方寝てしまうわ。そうしたら今度は起きたら夜中よ」
母はえらい剣幕で拒んだ。昼寝しないことによって精神が引き裂かれ、均衡が保てなくなる、そんな物言いだった。
「リズムが崩れることなんて誰にでもあることさ。騒ぐほどのことじゃないよ。それを繰り返しているうちに一巡して、きっと元に戻るよ」
「そんなのまともじゃないわ。朝起きて夜寝る。そして大切なのは一時間のシエスタをとることよ」母は憐れむように僕を見た。「シエスタって知らない? 本場のスペインでは業務中に昼寝時間を設けているところもあるのよ」
「そういう会社もあるにはあるけれどね。本来は仕事をしないだけで昼寝するとは限らないんだ。だから、今僕と喋ってるのもシエスタなんだよ。僕に至っては年がら年中シエスタみたいなもんだ」
僕は自嘲気味に笑うと、そろそろ勘弁願いたいな、といった具合に床に置いていたヱビスの缶ビールを手にした。爪を立ててプルタブをひっぱると、ヱビスビールはぴゅしゅうと小気味のいい音をあげた。一口呑み、伏せていた『ロリータ』を開く。
「夜通し不眠で悩んでいる人もいるんだよ。昼間の一時間じゃない、一晩中だ。それに比べたら蚊ほどに小さなことじゃないのかな」
「蚊を軽んじちゃいけないわ。人間は蚊によって死に至るのが一番多いの。年間どれだけのヒトが亡くなってると思う?」神妙な顔つきで母は言った。「七十万人よ。七十万! 蚊を笑うものは蚊に泣くの。だからね、あなたもそれくらいこの問題は大事なことだってわかってほしいの」
「詭弁だ」僕は笑いながらヱビスを啜る。「それ、WHOの統計だったね。僕はね、一位が蚊で良かったと思っているくらいなんだ。だってさ……その次がヒトなんだよ。サメでも蛇でもない、ヒトなんだ。同じ種族でここまで殺し合ってるなんて人間以外にはいないんじゃないかな。とても哀しいことだよ」
僕はそう言うと、字面の中からロリータの行方を追った。
「かあさんも哀しいわ。あなたが小さい頃は泣きやむまで抱っこしてあやしたのよ」
「悪いけど憶えていないんだ」
「かあさんは憶えてるの。事実そうなの」
「記憶ほど曖昧な事実はないさ。お互いの主義主張がすんなりと通るなら慰安婦問題も尖閣諸島問題も発生しないよ」
「歳を重ねるごとに偏屈になってくわね」
「成長と言ってほしいな」
それから母は黙っていた。一分、二分と扉の前で突っ立っていた。
僕は気にしないで、本を読み進めた。五分、十分と経過する。
まだいた。
僕は本を閉じ、「酒でも呑んだらどうだい?」と痺れを切らして話しかけていた。
「未成年のくせに何を言ってるの」
「六年と一週間前、めでたく二十歳を迎えたところだよ」
「あら、そうだったかしら」
母は僕の誕生日を忘れている。年齢さえも。いや、そもそも忘れたのではなく、憶えていないのだ。一度だって誕生日を祝ってもらった記憶もなければ、我が家には写真も存在しない。小学生の頃、同級生の誕生日会に招待されたことがある。庭池で鯉が泳いでいるような比較的裕福な家庭だった。同級生の母親がホールケーキを焼き、僕達は手渡されたクラッカーを鳴らした。
あれには仰天した。本当に仰天した。
しかし、羨ましいとは思わなかった。僕の家にはクラッカーがない、誕生日を祝わない。庭に池がない、鯉を飼わない。それと同じだ。
「かあさん、お酒なんかに頼らず自分の力で眠りたいの」
「僕に頼ってるじゃないか」
「いいじゃない、息子なんだから」
母の言う意味が少し理解できなかった。僕は酔っ払っているのだろうか。僕がおかしいのだろうか。残りのヱビスを呑み干し、次へと手を伸ばす。あっという間に空き缶が四つ並んだ。
なんらかの天変地異でユーラシア大陸とアメリカ大陸が激しく衝突する。互いの異文化が流れ込む。僕の中で、イズレイル・ザングウィルが提唱したメルティング・ポットのように母のアイデンティティーを理解しようと努めた。
「わかったよ。じゃあ、かあさんが眠れるために僕は何ができるだろう?」
「ロバート・マンチって知ってるかしら。彼の創った物語に『ラヴ・ユー・フォーエヴァー』っていうのがあるの。絵本でウチにあるんだけどね、かあさんあんな風に眠りたいわ」
「それに眠れるヒントが載ってるんだね」
母は首を傾げて言った。「そうね。きっと……載ってないわ」
アルコールでふやけた僕の脳ミソがますます混乱した。
母はまごまごする僕を見つめ、はっと口を縦に大きく開いた。「きっと枕がよくないせいよ」と、持っていた枕を恨めしそうに睨みつけた。
「それを買ったのはいつなんだい?」
「いつだったかしら。少なくとも五年は前ね」
「五年も寝ていたのなら充分だよ。枕に問題はないんじゃないかな」
「そんなことないわ。質のいい睡眠は適度な運動と枕がポイントだって『日経ウーマン』で読んだことがあるの。だから、枕を買いに行きましょう」母は僕の手を引いた。
「え、僕もかい?」
「あたりまえじゃない」
僕は浅く溜息を吐いた。「僕は今日までにこの小説を読み終えたかったんだ。ビールをちびちびと呑みながらね。読み終わったら、口笛でも吹きながら近所を散歩しようと思ってたんだ。『上を向いて歩こう』を吹きながらぶらぶらとさ。それがどうだい。ビールはもう残ってないし、酔っ払ったせいで舌がうまく回らないんだ。これじゃあ、口笛なんて吹けやしない。僕の予定は台無しだ」
「かあさんはね、あなたが仕事をしなかろうが、昼間からお酒に入り浸ろうが構わないけどね。シエスタを妨げることだけは許せないわ。絶対にね」
なんだか頭が痛んだ。「なんだか頭が痛いんだ」
「つべこべ言ってないで、早く準備して来なさい」
「傲慢だ」
「そうね。ちょっぴり傲慢なの」
僕は深く溜息を吐いた。
その3「ポカンとなったアンポンタン・ポカン」へ続く